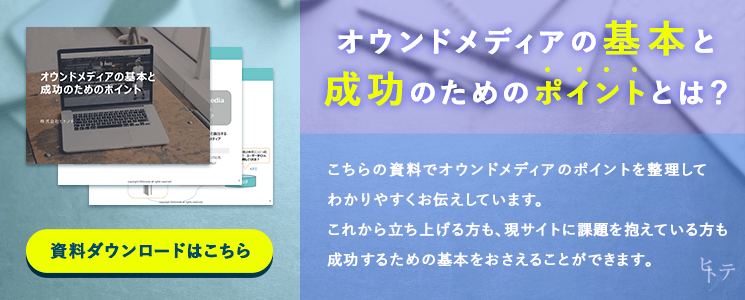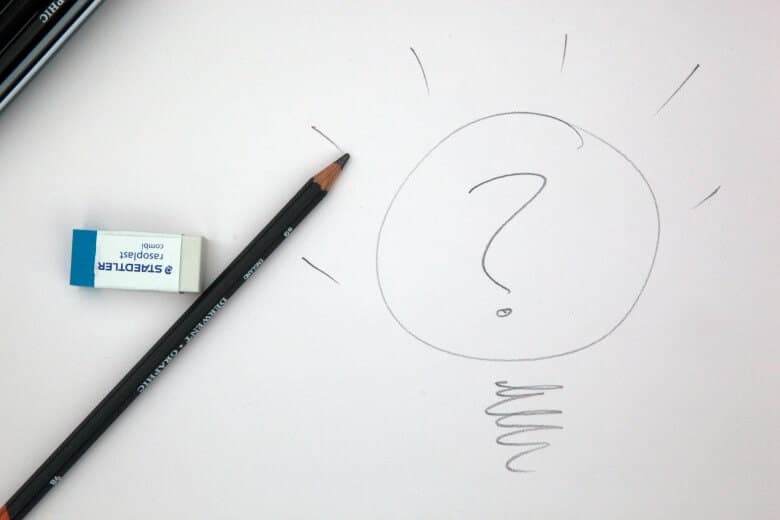Webコンサルティングを依頼する意味とは?選定の注意点まで解説

こんにちは、株式会社ヒトノテ代表の坪です。弊社は企業様のWebマーケティングの課題解決をご支援する、Webコンサルティングの会社です。
Webコンサルティングをご依頼いただく理由は企業によって様々ですが、私どもがコンサルティングをしていて感じるのは、以前に比べ依頼者側の知識レベルが高まっているということです。
依頼者側に知識があるのならば、わざわざWebコンサルティングを依頼する必要がないと思われがちですが、実はそうではないんです。
今回は弊社が考える、Webコンサルティングを依頼する意味・意義と依頼する際の注意点について、ぶっちゃけてご紹介をしていきます。
この記事の目次
Webコンサルティングの仕事とは
Webコンサルティングの仕事は大きく分類すると以下の3点です。
①Webマーケティングの”戦略”についてのコンサル
事業やサービスの目的達成のために、どのような方向性でWebの活用をしていくのかをコンサルティングします
②Webマーケティングの”組織”についてのコンサル
Webマーケティングの戦略を実行していくために、どのような組織・人材が必要なのかをコンサルティングします
③Webマーケティングの”施策”についてのコンサル
Webマーケティングの戦略を実行していくために、具体的にどのような施策を打って行くのかコンサルティングします
Webマーケティング全体を見る場合もあれば、SEO、CRO、広告、SNS活用など特定分野に特化してコンサルティングをしている会社も存在します。
いずれの場合もクライアントにWebマーケティングに関する知識を伝え、その知識をもってマーケティング施策などを実行していくのが、Webコンサルティングの仕事だと考えています。
コンサルティング会社の中には、コンサルティングだけでなくWebマーケティングの周辺業務、例えば広告の運用代行や、サイト・コンテンツ制作などをワンストップで請けるところも増えてきています。
余談ですが弊社ヒトノテも広告の運用代行や制作業務も行っており、ワンストップでWebの課題解決が可能な会社の1つです。
Webコンサルティングと一言で言っても、ご説明したように広い意味を持っているので、社内のリソースや状況に応じて、どこまでコンサルティングをお願いしたいのか?というの整理しておくと良いでしょう。
なぜ、Webコンサルティングの価値が下がっているのか
Webコンサルティングはいらないと考えている方も多いのではないでしょうか。実際、近年ではWebコンサルティングの価値が下がっているともいわれています。ここからは、Webコンサルティングがこのように評価されている背景や理由をぶっちゃけて解説します。依頼を検討する際に、参考にしてください。
情報が簡単に手に入るようになった
10年以上前であれば、Webマーケティングのノウハウをインターネットで調べても欲しい情報に辿り着けなかったり、辿り着けても真偽の判断が難しい情報も多かったのですが、
近年、インターネット上にはWebマーケティングの情報が溢れています。
Webマーケティングに関するマニアックな内容でも、Googleで検索すればすぐに情報が手に入りますし、SNSのタイムラインなどでも情報が流れてくるので社内のマーケティング担当者にとっては以前より情報収集が容易になったと言えます。
事業会社がインハウスでWebの専門組織を作るようになった
もともと内製化をしていたWebマーケティング業務をインハウス化する潮流もコンサルティングの価値を下げている要因の1つです。
かつて日本の事業会社では、複数の職種を経験するゼネラリスト職が出世・昇給しやすい傾向にありましたが、近年は逆にエンジニアなどのプロフェッショナル職が評価される傾向にあります。そのため、事業会社の中で働く側も、ゼネラリストではなくプロフェッショナル職としてキャリアを積んでいきたいという方が増えてきているのが実情です。
私が知る限り、評価形態や待遇を理由に広告代理店から事業会社側へ転職するプロフェッショナル職が明らかに増えていると思っています。
お願いしても「何も変わらない」と思われている
近年ではSEOやCRO、グロースハックの重要性を会社が理解し、その分野でコンサルティングしてほしいというニーズが強まったきたもの、これらの施策を実行し成果を出せているコンサルティング会社は少ないというというのが現状です。
従来、Webサイトの管理や改修と切り離しやすい広告周りのコンサルティングが大半でしたが、SEOやCROはWebサイトの改修が発生するため、社内のエンジニアや決裁者との接続が欠かせません。これらがうまくいかずに、コンサルティング契約をしても何も変わらない・成果を出せないという失敗体験から、Webコンサルティングにネガティブな印象を持っている方が多いように思います。
Webコンサルティングを依頼する意味
以下ではWebマーケティングをWebコンサルティング企業に依頼する意味やメリットを解説します。
時間をお金で買う
事業会社側にWebマーケティングの知識がない場合に、社内でそのような人材を育成するより外部の専門組織にお願いすることで育成の時間とコストをショートカットできます。
また、知識だけあっても、それを実行に移せなければ意味がありません。
良いWebコンサルタントであれば、知識を実行に移すためのノウハウも持ち合わせています。これらのノウハウについても社内で蓄積するには時間が掛かりますので、それを短縮するためにWebコンサルティングを依頼するという考え方もできます。
Webマーケティング人材の不足と採用の不確実性
Webマーケターと呼ばれる人材は日本国内に約2万人です。それに対して、Webマーケティングが必要な会社は全国に60万社存在し、人材不足であることは明らかです。また、Webマーケターを採用しても、社内でパフォーマンスが出せなかったり、企業風土が合わずに退職していくケースが後を絶ちません。
社内にいる人材の代替手段として、外部へWebコンサルティングを依頼する企業も多いです。
Webコンサルタント1人あたりの費用は、内部の人件費より高いことが多いですが、採用費や育成コストを考えると外部パートナーにお願いすることが割高とは限りません。
Webコンサルティング会社を選定する上での注意点
Webコンサルティングを依頼する際、どの企業にするかの判断は非常に重要です。事業者によっては、本質的なアドバイスや必要なコンサルを行ってくれない可能性もあります。以下では、コンサルティング会社を選定する上での注意点を解説します。
実行力が伴うコンサルティングをやってくれるのかどうか
Webコンサルティング会社を選定する際には、その会社が実行力を持っているかどうかを見極めする必要があります。
実行力がある会社を見極めるポイントは以下3点です
- サイトのデータ分析ができるか
- 社内のエンジニアとのコミュニケーションがとれそうか
- 施策を打って終わりではなく、振り返りをしてPDCAを回せそうか
本当にWebコンサルティングを売りたい会社なのか
そのコンサルティング会社に、ツールなどアップセルにつかえる商材がある場合は注意です。そのツールを売ることを主目的にWebコンサルティングをしていると、コンサルティングを受ける側の目的とすり合わず、本質的な提案をしてもらえなったり、ツールを買わせるための分析データなどが出てくる可能性もありますので注意です。
提案施策の理由や、企業からのWHY?にロジックをもって説明できるか
理由や仮説がない施策は効果の振り返りもできませんし、提案を受けた方がその施策の説明がしずらいため社内の共通認識を持って意思決定をし、進めていくことが難しくなります。
逆にそのコンサルティング会社がトレンドや感覚に沿った提案しかできない場合うまくいかないことが多いと言えます。契約前のコミュニケーションの中で、提案内容に対するなぜ?を応えられるか見極めておきましょう。
できないことを出来ないと言えるか
コンサルティング契約の商談時に、自分たちのケイパビリティの外にあることも「できる」と言って受注をし、いざ取り組みを開始したら期待していたことを何もしてもらえない!というパターンも稀にあるそうです。ビジネス全般に言えることですが、できないことを正直に言ってくれる会社のほうが信頼できるのはもちろんですし、Webサイトの施策においては、うまくいったこと・いかなかったことを正しく捉えて、次に活かしていくことがサイトの成長に繋がりますので、それができるかどうかを事前に見ておきましょう。
まとめ
Webコンサルはいらない、依頼しても成果に繋がらないという方は多いですが、実際には状況に合わせた座組の組み方によっては大きな成果に繋げることができます。
今の時代はWebマーケティングに関する情報が溢れていますので、体系的な知識の提供だけではなく実行力を伴ったWebコンサルティングができる会社を探すことが成功の鍵だと考えています。
今回ご紹介した会社選定の注意点を参考にしつつ、良いパートナーシップを築いてください。

執筆者:坪昌史
株式会社ヒトノテの代表取締役CEO。 エンジニアとしてキャリアスタートし、サイバーエージェントのSEO分析研究機関を経て、リクルートの横断マーケティング組織のマネージャー&全社SEO技術責任者を務める。その後、独立しSEOを中心としたクライアントの課題解決を行う。2017年、株式会社ヒトノテを創業し、様々な企業のウェブマーケティングの支援を行う。
おすすめの関連記事
─ 記事カテゴリから探す ─
元事業会社のコンサルタントがご提案
WEBマーケティングの無料相談
人気記事ランキング
-
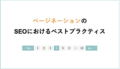
2024.04.25
ページネーションのSEOにおけるベストプラクティス
-
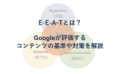
2024.04.22
E-E-A-Tとは?Googleが評価するコンテンツの基準や対策を解説
-

2021.12.06
レスポンシブデザインの最適ブレイクポイントとは?メディアクエリの書き方も解説
-

2021.12.22
【徹底比較】さくらのクラウドとAWSの特徴・機能・料金の違いを解説
-
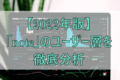
2022.02.21
「note」のユーザー数や年齢層を徹底分析!【2022年版】
-

2021.07.09
Webコンテンツにおける正しい引用の書き方をマスターしよう!
-

2022.03.10
Googleインデックスの登録・確認方法を解説!サーチコンソールを使ってクロールリクエストしよう