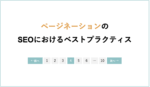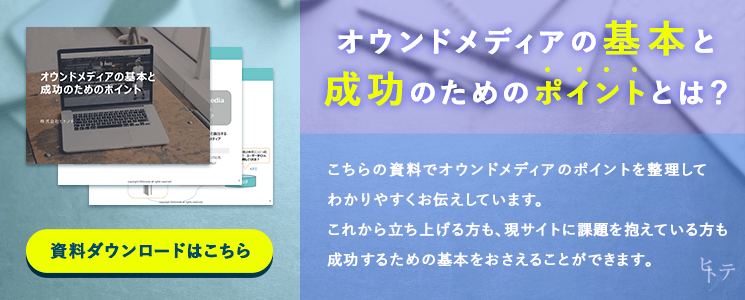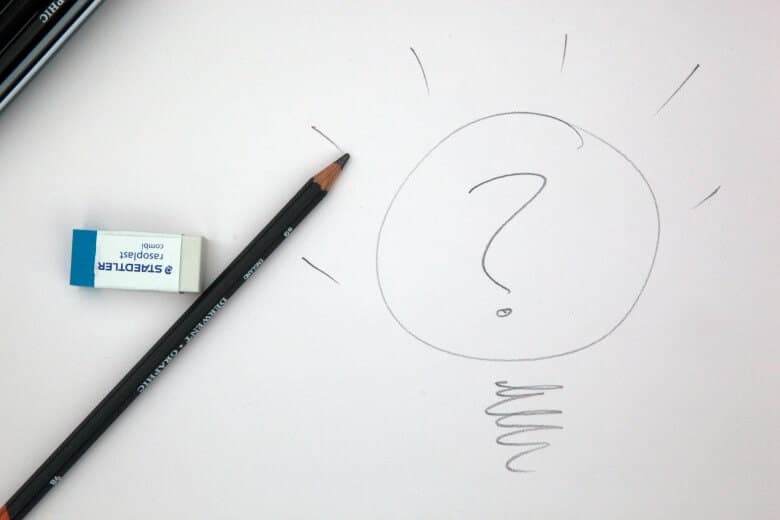SEO内部対策の基本|実施すべき17施策と注意点

SEO内部対策は、自社のウェブサイト内部で行うSEO施策のことです。検索エンジンのクローラーがサイトを効果的に検索し、ランキングを向上させるための重要な施策となります。また、内部対策を行うことでユーザビリティの向上も期待できます。
この記事では、SEO内部対策の具体的な方法と注意しておきたいポイントを解説します。
この記事の目次
SEOにおける内部対策とは?
SEO内部対策とは、サイト内のコンテンツやソースコードなどの内部構造を対象とした対策のことです。
SEO内部対策を行うことにより、検索エンジンのクローラーがウェブサイトを正確に理解できるようになります。検索エンジンのクローラーに発見されなければ検索結果に表示されることはありません。
ウェブサイトのページ構造やコンテンツを最適化することで、検索エンジンのクローラーが正確にウェブサイトを理解し、正しいインデックスを行いやすくなります。
近年の検索エンジン、特にGoogleは内部対策を重要視している傾向にみられます。また、年々アルゴリズムが複雑になっているので、ただ施策を行うだけでは効果が得られない可能性も考えられます。
まずは内部対策がいかに重要なのか、その理由をしっかりと理解してから対策を行うようにしましょう。
内部対策と外部対策の違い
SEOの内部対策は、先述した通りサイトを改善していくことでSEOの効果を高める対策です。
ソースコードを最適化したり、ユーザビリティを高めたり、サイト構造を整理したりすることで、検索エンジンから評価されやすいサイト作りを行うことを内部対策と呼びます。
一方の外部対策は、他サイトやSNSなどから被リンクを集める対策です。どちらの対策もSEOにおいて重要ですが、まず行ってほしい対策は内部対策です。
内部対策は上位表示のために必須
SEOの中で、内部対策は必須と言ってよいほど重要な対策です。
なぜ内部対策が重要視されているかというと、検索エンジンが評価するのは、サイト内のコンテンツだからです。
GoogleやYahoo!などの検索エンジンは、クローラーと呼ばれるネット上の情報を自動で収集、分析、整理を行うプログラムを使って、サイトの情報収集と評価を行っています。
しかし、クローラーは人ではなくいわば機械のため、人間のようにサイトを認識できません。クローラーでもサイトの内容が分かるようにするには、さまざまな手法を用いてサイト内コンテンツを理解しやすくしてあげる必要があります。
これがSEOの内部対策にあたるのです。内部対策を行うことで、クローラーに正しくサイト内の情報を伝えることができ、正しい評価を受けることができます。
せっかく良いコンテンツを作り上げても、評価をしてくれるクローラーに伝わらないのであれば意味がありません。正しい評価を受けるために、SEOの内部対策は必要であり重要と言えます。
内部対策として行うべき施策は少なくありませんが、行うか行わないかではクローラーからの評価が大きく異なることもあります。
手間だと思わず、しっかりと対策をしておきましょう。
検索順位が決まる仕組み
内部対策が重要であることはご説明しましたが、より理解していただくために、検索順位が決まる仕組みを、ご説明します。
- クローラーによる巡回
まずはクローラーにより、サイト内の情報が収集されます。クローラーとは、サイト内の文章や画像などの情報を自動で収集し、検索データベースを作成する巡回プログラムを意味します。クローラビリティという言葉もよく耳にするかと思いますが、クローラビリティとは、クローラーのWEBページの見つけやすさを指します。これらの説明から、クローラーにWEBページを見つけやすくすることが、SEOとしても重要だということが分かっていただけるかと思います。
- サイトの内容を正確に伝える
クローラーがサイトに巡回してきたら、次にクローラーが行うのはサイト内情報の収集です。そのため、いかにサイト内の情報をクローラーに対して正確に伝えるか、ということもSEOとして重要になります。正確に伝えるためには、hタグやtitleタグをきちんと設置したり、最も伝えたい・評価してもらいたいポイントが分かるような構成にする必要があります。
- サイトの要素を評価してインデックス登録(順位決定)
最後に、収集したサイト内の情報を評価をし、インデックス登録をし、順位が決まります。インデックス登録をする=検索結果に反映させる、ということになります。インデックス登録がされなければ、いかなるキーワードで検索しても検索結果に出てきません。高い評価をしてもらうには、評価の対象となる要素を一つずつチェックし、改善していくことになりますが、これをSEO(検索エンジン最適化)といいます。
SEO内部施策①クローラーの巡回を促す
では、実際にどのような内部対策が必要なのか、用途ごとに重要な施策をご紹介していきます。
まずご紹介するのは、クローラーの巡回に関する施策です。
コンテンツを理解してもらうためには、クローラーにサイトへ来てもらい、全てのコンテンツを見てもらわないといけません。コンテンツを理解してもらう前の第一歩として、そもそもクローラーがサイト内を巡りやすくしておく必要があります。
クローラーがサイト内をしっかりと見て回れるように、以下のような対策を行っておきましょう。
XMLサイトマップの送信
XMLサイトマップとは、ユーザーが見るものではなくクローラー向けのサイトマップです。サイト内にどのようなページがあるのか一覧にしたもので、Google サーチコンソールからGoogleに送信ができます。
XMLサイトマップを送信することで、Googleにサイトの実態を知らせることができ、サイト内に存在するページも知らせることができます。
クローラーは、このサイトマップを1つの参考にサイト内を巡っていくため、サイトマップの送信はクローラーのサイト巡回に非常に役立ちます。
XMLサイトマップは、作成用のツールなども用意されています。ツールを使えば簡単に作成ができるので、必ずサイトマップを作成して送信をしておきましょう。
適切な内部リンクの設置
内部リンクとは、同サイト内のページにリンクを貼ることです。
適切な内部リンクはクローラーの回遊率も向上でき、評価されやすくなるというメリットもあります。クローラーは、トップページから順番に巡回していくのではなく、蜘蛛の巣のようにリンクを伝って巡回していきます。そのため、内部リンクがなければたどり着けないページが生まれ、評価されにくくなってしまうのです。
しかし、内部リンクは、むやみに貼ればいいというわけではありません。「関連性の高いコンテンツのリンクを貼る」ことや「アンカーテキストでリンクを貼る」ことが大切です。関連性の低いコンテンツとの内部リンクは、不正に検索順位を操作しようとしていると認識されてしまいます。「ユーザーやクローラーが巡回しやすいように内部リンクを設置」するという目的を忘れないようにしましょう。
URLの正規化(リダイレクト、canonical)
サイトを作成すると各ページにはURLが生成されます。
1つのページに1つのURLというのが通常ですが、実はシステムなどの関係上で1つのページに対して複数のURLができてしまうことが多くあります。
例えば、http://sample.com/とhttps://sample.com/は、ページにあるコンテンツは同じであっても、「http」と「https」という異なるURLになってしまいます。このような時、クローラーは2つのページをそれぞれ それぞれ別のサイトとして 評価するため、評価が分散してしまう可能性があります。
これは上記の場合だけでなく、内容がほぼ同じであるページやwwwのありとなし等でも当てはまります。
その際、サイトの管理者側から正しいURLをあらかじめ伝え、評価対象を1つのURLに絞ることができれば、クローラーも迷うことなく正規URLを評価、インデックスすることができます。
そこで使用するのがリダイレクトやcanonicalといった手法です。
リダイレクトは、「wwwの有り無し」や「http、https」など異なるURL形式でアクセスしても行き着くURLを1つに限定する手法です。
canonicalは、ソースコードに記述して正規URLをクローラーに教える手法です。
インデックスをしてほしくない方のURLから正規URLにリダイレクトをしておけば、クローラーはそもそもインデックスをしてほしくないURLの中を見たりせず、正規のURLにたどり着くことができます。
もしくは、正規URLを表記したcanonicalを設置しておくことで、クローラーに正規URLを伝えることができます。
▼関連記事
SEOにおいて重要なheadタグの書き方 タイトル、カノニカルetc
robots.txtの使用
robots.txtは、クローラーにサイト内でアクセスをしてほしくないページや、XMLサイトマップファイルの位置を知らせる事ができるファイルです。
例えば、WordPressなどでサイトを作成している場合、管理画面などのURLは特にクローラーに見てほしいわけではないでしょう。
それよりもサイト内のコンテンツを見るために時間を使って欲しいと思う場合に、robots.txtを使えば特定のURLやファイルへの巡回を拒否することができます。
他にも、XMLサイトマップの設置場所を知らせることもできるため、クローラーのサイト内巡回の手助けになります。
ここで1点気をつけたいのが、robots.txtでクローラーの巡回を拒否したからといって、検索エンジン上に表示されないというわけではないこと。検索エンジン上に表示されないようにしたい場合は、noindexを使用するなどして別の対応が必要になります。
パンくずリストの設置
パンくずリストは、ページ上部や下部に表示する内部リンクのリストです。パンくずリストの有用性は、Googleのスターターガイドにも明記されています。
パンくずリストという名前は、『ヘンゼルとグレーテル』の森で迷わないようにパンくずを置いて歩くシーンから名付けられました。その由来の通り、パンくずリストは「HOME>COLUMN」のようにサイト内の構造を示す道標の役割を担っています。
また、そのページがサイト内ではどのような位置づけなのかを示すだけでなく、サイトのトップやひとつ上の階層のページにすぐ移動ができるため、サイト内巡回に役立ちます。
ユーザー、クローラー両者にとってサイトの階層を理解しやすいうえに、クローラーのページ移動がしやすくなるため、パンくずリストは設置をしておくと良いでしょう。
シンプルな階層設計
ほとんどのサイトにはトップページだけでなく、下層ページがあり階層が分かれていると思います。この階層はユーザー、クローラーにとって重要で、求めているコンテンツへ素早くたどりつけるような階層である必要があります。
Googleは、「ユーザーができるだけ簡単にたどり着けるように」することを求めています。「簡単」とは、つまり「クリック数を少なくする」ことだと解釈できます。
一般的にはどのページにも3クリック以内に到着できるような設計が良いとされています。今いるページから読みたいページまでに4クリック以上かかる場合は、サイトの構造を見直しましょう。
例えば、関連する情報をカテゴリごとに分けて階層を作れば、ユーザーは必要な情報があるところだけを見ることができます。クローラーも、その階層にあるコンテンツがどのようなジャンルのコンテンツなのか理解をしやすくなるでしょう。
しかし、階層を細かく分けすぎてしまうと、逆にどこを見たらいいのか迷ってしまうユーザーもいるかもしれません。階層が深く、クリック回数が増えるとユーザーが不便に感じてしまい、離脱につながる可能性があります。
クローラーもサイトを回遊するために時間を要してしまい、どちらからも評価されなくなってしまうでしょう。サイトの階層を考えるときは、本当にそのカテゴリ分けが必要なのかどうかを考えながら、分かりやすくシンプルな設計を目指しましょう。
また、ひと目でわかるようなカテゴリ名を付けることも大切です。
SEO内部施策②サイトの内容を正確に伝える
ここまで、クローラーをサイトに呼び込み、巡回をしてもらうための施策を紹介しました。
クローラーがサイトに来てくれるようになったら、次に重要な点はコンテンツを理解してもらうことです。クローラーがせっかくサイトを巡回してくれても、中に書いてある内容が正しく伝わらなければ評価につながりません。
そのため、サイトの内容はクローラーに伝わりやすくしておく必要があります。
ここでは、サイト内容をより正確に伝えるためにやっておくと良い施策をご紹介します。
titleタグの最適化
titleタグは、検索結果上にも表示されるページのタイトルを指します。
ページ内のコンテンツとしては表示されませんが、titleタグを設置しておくことでクローラーがタイトルを読み取り、ページの内容を把握するだけでなく、検索結果上にも表示をしてくれます。
ただし、検索結果上に表示される文字数は限られているため、長すぎると表示されない可能性もあります。
titleタグはそのページで一番重要な情報を簡潔に伝えられる内容にしましょう。一番重要な情報というのは、自然とそのページで対策をしているキーワードと重なるはずです。
クローラーやユーザーがすぐにキーワードを見つけられるように、titleタグには対策キーワードを入れておくと良いでしょう。また、検索結果上でより目につきやすいように、タイトルの前半にキーワードを入れておくことも重要です。
これらのポイントは、Googleも推奨しています。Google検索セントラルの「検索結果に効果的なタイトルとスニペットを作成する」において、「ユーザーが一目でわかるように」と表現されているように、Googleはユーザーの利便性を重視しています。
検索エンジンに評価されるためには「対策キーワードを入れる」などのテクニックも多少は必要です。しかし、クローラーを重要視するあまり、同じキーワードを何回も使用したり、ページとは関係ないキーワードを入れるなどを行うと、検索順位が下がるおそれがあるため注意しましょう。
見出しタグの最適化
文章を読むときに、適切な見出しがあると内容を理解しやすくなります。これはWeb上のコンテンツも同じで、見出しタグを活用してコンテンツを整理しておくことで、ユーザーやクローラーはコンテンツの理解を深めることができます。
見出しがない、あるいは関係のない見出しがついていては、ユーザーが今何の話を読んでいるのかわからなくなってしまいます。分かりやすいコンテンツを作るためには、ユーザーがすぐに理解できる文章の見出しを付けることと、h1、h2のように数字を用いて見出しの階層を作ることが大切です。
見出しタグはh1からh6まであり、数字が大きいほど詳しい内容が書かれていることになります。そのため、見出しタグはただ使うだけではなく、コンテンツの内容に合わせて意味のある所で使う必要があります。
例えば、h1、h2と続いた後にh5を使うと、コンテンツがいきなり詳しくなってしまうことになり、ユーザーもクローラーも内容が理解できません。数字は順番通りに正しく使い、コンテンツの内容を丁寧に分けていくようにしましょう。
meta descriptionの活用
meta descriptionはメタタグの1つで、ページの概要をクローラーに伝えるためのタグです。
meta descriptionもtitleタグと同じようにページ上では表示されませんが、クローラーにtitleタグでは伝えきれなかったコンテンツの内容の補足として情報を伝える事ができます。
また、検索結果上のtitleの下にスニペットとして表示されることもあり、ユーザーに対してもコンテンツ内容をアピールすることができます。文字数もtitleタグより長く書くことができるため、重要なキーワードと合わせてページ内容を細かく伝えることが可能です。
例えば会社HPのコラム記事の場合、検索結果でも会社のことをアピールしたいと思う方も多いと思います。しかしmeta descriptionは、あくまでもそのページを説明するためのものです。会社紹介の定型文を載せるのではなく、「~について〇〇株式会社が紹介します」のようにコンテンツ内容を踏まえた上で必要に応じて会社名も訴求するようにしましょう。
検索結果で表示された時に、ページの内容に興味を持ってもらえるようなmeta descriptionタグを設置すると、クリックされる回数も増えるかもしれません。
alt属性の設定
サイトの内容をより視覚的に伝えるために、コンテンツ内に画像を使用する場合も多いでしょう。しかし、場合によっては画像が表示できない環境があり、ユーザーが画像を見ることができない可能性もあります。
そんなときに、一体どのような画像が設置されていたのかを伝えるためにalt属性を使い画像内容を記載しておくとよいでしょう。
alt属性は「代替テキスト(alternative text)」という意味があり、画像の意味を伝えるために用いられます。例えば、図表などの画像を前提に説明文を記載している場合、画像が表示されないとコンテンツ全体の意味を損なってしまいます。そのため、alt属性でおおまかな内容を伝えることが大切です。alt属性は読み上げ機能でも用いられるため、視覚に障がいのある方へのサポートとしても重要です。
また、alt属性に書かれた内容は、ユーザーだけでなくクローラーにとっても画像理解の手助けになります。一体どのような画像が使われているのか、わかりやすく記載をすることでコンテンツへの理解も深まります。
ただし、alt属性もむやみに記載をしているだけでは十分な情報が伝わりません。その画像を的確に表現できるような簡潔な言葉を選んで記載するようにしましょう。
構造化データのマークアップを行う
構造化マークアップをすることで、検索エンジンにサイトの情報を詳細に伝えられます。構造化マークアップとは、コンピュータシステムが読み取れる形式でHTMLに情報を記載することです。構造化マークアップすることで、検索結果に特定の情報を表示させる「リッチリザルト化」ができ、ユーザーにクリックしてもらえる可能性が高まります。
例えば「東京都千代田区〇〇」のような文章は、人間が読めば「住所」だと認識可能です。しかし、検索エンジンは情報の意味までは理解できません。そのため、「名前(name)」「住所(address)」「電話番号(telephone)」などといった「タグ」を用いて、情報の意味を伝える必要があります。
構造化マークアップは、HTMLを直接編集する方法と構造化データマークアップ支援ツールを使用する方法があります。詳しくは、構造化データとは?マークアップを行うメリットやSEOへの影響とはをご覧ください。
ページネーションの設置
ページネーションとは、長いコンテンツをいくつかのページに分割する時に使います。
例えば、ショッピングサイトのカテゴリ一覧や、ブログ記事の一覧などは非常に多くのコンテンツがあるため、適度なところでページを分割しているサイトも多いでしょう。どれくらいのコンテンツがあるのか、ユーザーもページ数から判断することができます。
このようにページを分割するとURLは別々になってしまうため、続き物のコンテンツであることを伝えるためにページネーションタグも合わせて使用することも可能です。
ただし、Googleはページネーションタグのサポートを2019年で廃止しています。現在は一部のクローラーにしかサポートされていないため、ページネーションタグを新たに設置するかどうかは、作業量によって判断をした方がよいかもしれません。
ページネーションを行う場合は、ユーザーにとって見やすいかどうかを考えて行うようにしましょう。
SEO内部施策③ユーザビリティを向上させる
Googleは、ユーザビリティやユーザーエクスペリエンスを大事にしています。
特にスマホが普及している今は、スマホからの閲覧がストレスなくできているかを重要視しており、現在Googleが主に順位の評価対象としているのはスマホ向けサイトのコンテンツです。
そこで、ここからは特にユーザビリティを向上させるための施策をご紹介します。
モバイル最適化
先述したように、Googleは特にスマホから閲覧した際のユーザビリティを大切にしており、スマホから快適に閲覧できるサイトを評価する傾向にあります。
Googleはスマホを「モバイル」と呼んでいるため、モバイルの最適化はつまり、スマホ向けサイトの最適化ということになります。
以前はパソコンユーザーがメインであり、モバイルユーザーに対する施策はプラスアルファとして「やっておいたほうが良い」程度の認識でした。
しかし近年は、上記の通り「モバイルが主流」となっており、モバイル最適化の重要度が高まっています。モバイルでも見やすいページが当たり前になっているので、モバイルから見にくいページはどれだけ良い情報が記載してあっても離脱されてしまう可能性が高いです。
そのため、パソコンからのユーザーだけではなく、スマホユーザーが多いことも考えたデザインやコンテンツ配置を心がけましょう。現在ではパソコンとスマホで同じコンテンツを表示する「レスポンシブデザイン」も主流です。
今からサイトを作るという人は、レスポンシブデザインでのサイト制作を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
表示スピードの改善
もう一点Googleが重要視しているのが、サイトの表示スピードです。
Googleの調査によると、サイトをクリックしてから画面が表示されるまでの時間が3秒を超えると、約40%のユーザーがサイトを去ってしまうと言われています。
ユーザーがサイトを離れてしまわないよう、ページの表示速度は確認、改善を行うことをおすすめします。
また、Googleも上記のような状況を受けて、ページの読み込み速度をサイトの評価基準のひとつとして取り扱うようになりました。表示スピードの改善は、ユーザーのためだけではなく、検索エンジンから評価を受けるためにもなるのです。
SEO内部施策④コアウェブバイタルの改善
Googleは、 2020年の11月10日に、Google検索セントラルにて、Core Web Vitals(コア ウェブ バイタル)という指標を、2021年5月に正式に検索結果のランキング要因に組み込むことを発表しました。コアウェブバイタルとは、以下3つの要因の総称です。
- LCP(最大コンテンツの描画)
- FID(初回入力遅延)
- CLS(累積レイアウト変更)
それぞれどういうものなのか、ご説明します。
LCP(最大コンテンツの描画)
ページの「読み込み時間」に関する要因がLCPです。
「読み込み時間」とは、ページ内のコンテンツがが表示されるまでの待機時間を意味します。どのくらい早くページ内のコンテンツを見ることができるのか、ということです。
ページの主要コンテンツが読み込まれたと思われるタイミングを測定し、ページ読み込み開始から、2.5秒未満が「良好」、4秒以下は「改善が必要」、4秒を超えると「不良」と判定されます。
FID(初回入力遅延)
ユーザーの「インタラクティブ性」に関する要因がFIDです。
「インタラクティブ性」とは、ユーザーがページ上で最初に行う、クリックやタップなどの操作における、インタラクティブ性や反応速度を意味します。
その反応速度を測定し、ユーザーが最初にページを操作する場合に感じる「インタラクティブ性」を数値化します。
ユーザーが最初の操作をしてからの反応速度が、100ミリ秒未満が「良好」、300ミリ秒以下は「改善が必要」、300ミリ秒を超えると「不良」と判定されます。
CLS(累積レイアウト変更)
ユーザーの「累積レイアウト変更」に関する要因がCLSです。
「累積レイアウト変更」とは、読み込み時に予期しないレイアウトの変更やズレがどの程度発生したのか、視覚的にページがどの程度安定しているのかを表します。
レイアウト変更を評価する際には、0から1の範囲で数値化します。
0は移動なし、1は変更が最大であることを示します。0.1未満が「良好」、0.25以下は「改善が必要」、0.25を超えると「不良」と判定されます。
さらに詳しくコアウェブバイタルについて知りたい方は、以下の記事で解説していますので、参考にしてみてください。
コアウェブバイタルとは?LCP・FID・CLSなどSEOに影響のある指標も解説
SEO内部施策を行う際の注意点
ここまでSEOの内部対策をご紹介してきましたが、度を超えてやりすぎてしまう、もしくは良いと思った行動でも、Googleの示すガイドラインに違反をしてしまうとペナルティを課せられることがあります。
「手動による対策」と呼ばれるペナルティを受けてしまうと、サイトの順位が下がる、検索結果から削除されるといった可能性もあります。
なかには、意図せずそうなってしまったというパターンもありますが、Googleは意図的でもそうでなくても公平にペナルティを課します。
そのため、SEOの内部対策を行う上では、次の点を注意しておきましょう。
隠しテキスト・隠しリンクの排除
ユーザーに見えない文字サイズ、または色などでサイト内に記載された文字やリンクを、隠しテキスト(隠しリンク)と呼びます。
実は、ユーザーにとって有益でないサイトでも、キーワードさえ詰め込んでしまえば上位表示ができた時代がありました。
そのため、対策キーワードや共起語をクローラー向けに設置し、ユーザーには見えないよう文字色やサイズ、装飾で隠してしまうことで不正に評価を得ようとしたサイトが存在しました。
これらの手法は現在違反とされており、ペナルティの対象になります。
例えば、意図せず配置した場所が画像と重なってしまい隠しテキストになってしまった、必要ないコンテンツをCSSで見えないようにした等、悪意がない場合でも違反行為と判断されてしまうことがあります。
ソースコード上に存在するコンテンツはすべてユーザーに見える状態になっているか、サイトをよく確かめておくようにしましょう。
キーワードの詰め込みに注意
先述したように、以前のGoogleではキーワードが多く入っていれば上位表示する傾向にありました。
しかし、現在はコンテンツの内容や情報を重視しているため、ただキーワードが入っているだけでは評価されません。あまりにも不自然にキーワードを多用していると、ユーザーが文章を読みにくいため、利便性が低下するとしてGoogleのガイドライン違反になる可能性があります。
キーワードを適切に使うことで情報が豊富なコンテンツになりますが、あくまでもユーザーが読みやすい自然な文章であることが前提です。
キーワードを意識しすぎるあまり、不自然に詰め込みすぎてしまわないよう注意しましょう。
重複コンテンツとならないように注意
同じような内容の記事は、検索エンジンに重複コンテンツと認識されてしまう可能性があります。
競合ページをコピーしたようなコンテンツはもちろん、同サイト内に似たようなコンテンツがある場合にも重複コンテンツとなることがあるので注意しましょう。
同サイト内に重複コンテンツがあると、被リンクが分散したり、検索結果に載りにくくなったりするデメリットがあります。重複コンテンツの可能性があるものは、状況に応じて削除・統合・noindexタグの付与などを検討しましょう。
ツールを活用してSEOの内部施策をチェック
Googleが無料で提供しているツールを活用することで、SEOの内部施策に問題が発生していないかを確認できます。
ここでは、「Googleサーチコンソール」と「PageSpeed Insights」の2つを活用したエラーの確認方法を紹介します。
Googleサーチコンソール|カバレッジエラー
Googleサーチコンソールを活用することで、カバレッジエラーについて確認ができます。
カバレッジとは、Webサイト内の各ページのインデックス状況を確認できる、Googleサーチコンソールの機能のこと。
インデックスの状況は、インデックス登録カバレッジレポートとして閲覧が可能です。
インデックスカバレッジエラーが起きたら、まずエラーの内容を確認し、その内容に応じて適切な対応をする必要があります。エラーをそのまま放置したままにすると、SEO評価に悪影響を与えてしまい、検索順位が落ちてしまう恐れがあるため注意が必要です。
次章では、よくあるエラーの種類とその内容について解説します。
エラーの種類
Googleサーチコンソールのカバレッジエラーのよくある例として、主に以下の4つがあります。
- サーバーエラー 5XX
- ソフト404エラー
- robots.txt
- noindex
それぞれのエラーと対処法の詳細については、以下の通りです。
| エラーの種類 | エラーの内容 | 対処法 |
| サーバーエラー 5XX | サーバーで何かしらのエラーが起こったことを表す | エラーの番号によってエラー内容がわかるので、原因を推測して対応 |
| ソフト404エラー | インデックスさせたいページがあるが、Googleからインデックス不要と判定された際に発生するエラー | インデックスさせたいなら、該当ページのコンテンツを充実させる |
| robots.txt | robots.txtによってクローラーのアクセスを制限している際に、エラーとして発生 | インデックスさせたいページにエラーがあるなら、ファイルを編集しクロールのブロックを解除 |
| noindex | noindexタグが設定されているため、クローラーがインデックスできないページが存在するときに発生 | インデックスさせたいコンテンツからnoindexタグを削除 |
Googleサーチコンソール|クロールの統計情報
Googlebotのクロール状況についても、Googleサーチコンソールで確認が可能です。
クロールの統計情報を見て、長期的な状況を確認しましょう。クロール数が減少している場合は、サイトに何らかの問題が発生している可能性が考えられます。
サーチコンソールの画面左にある「クロールの統計情報」をクリックすると、サイト全体の90日間のGooglebotの活動状況の確認ができます。具体的に、以下の3つのグラフが表示されます。
- 1日のクロールリクエストの合計数
- 1日の合計ダウンロードサイズ(バイト)
- ページの平均応答時間(ミリ秒)
それぞれについて詳しく解説します。
クロールリクエストの合計数
クロールリクエスト合計数は、上昇しているなら1日にクロールされたページ数が増えているため良い傾向です。日によって多少上下の動きはあるので、波は気にする必要はありません。
しかし、長期的に下降傾向になっている場合、Googlebotの巡回するページ数が減っている可能性が考えられます。このケースの場合、何かしらの問題が発生しているので、先程紹介した「カバレッジ」でエラーの内容を確認しましょう。
合計ダウンロードサイズ(バイト)
2つ目のダウンロードサイズ(バイト)」は、クロールされたページ数が増えるにつれて上昇するため、気にしなくても大丈夫です。
ページの平均応答時間(ミリ秒)
ページの平均応答時間(ミリ秒)は、最も重要な指標の1つです。
ページの平均応答時間は、ページをダウンロードするのにかかった平均時間のこと。ダウンロード時間が大幅に上昇しているときの要因として、サーバーの不調や一つひとつのコンテンツの容量過多などが考えられます。
そのまま放置しておくと、以下のデメリットがあります。
- Googlebotが多くのページを巡回できずに離脱する恐れがあり、クローラビリティにマイナス
- サイトの訪問ユーザーにも「表示が重い」と感じさせて離脱すれば、SEO評価も下がる恐れがある
数値が異常に上昇している場合、サーバーのスペック変更の検討やプラグインを使って整理するなどが対処法として挙げられます。また、社内にエンジニアがいるなら相談してみるのも良いでしょう。
PageSpeed Insights |Webサイトの表示速度
Googleが無料で提供しているPageSpeed Insightsを活用することで、Webサイトの表示速度や下落要因を分析できます。PageSpeed Insightsは、コアウェブバイタル(Core Web Vitals)を改善するためには必須です。
コアウェブバイタルとは、サイトの使いやすさを図るための3つのUX(ユーザー体験)指標のこと。具体的には、以下の3つです。
- LCP(Largest Contentful Paint):画像や動画など、ページの中で最も大きなコンテンツが表示されるまでの速度
- FID(First Input Delay):サイトの訪問ユーザーが行動を起こしたときに、ブラウザが反応するまでの時間を数値化したもの
- CLS(Cumulative Layout Shift):ページの読み込み時に発生したレイアウトのズレの変化量をスコア化したもの
表示速度が遅いとユーザーがストレスに感じ、離脱につながってしまいます。離脱率が高くなるとGoogleからの評価も下がり、SEO評価が落ちる要因にもなります。上記で挙げたコアウェブバイタルの3つの要素は、定期的に確認することが重要です。
SEOの内部施策を外注するメリット
SEOは奥が深く、知識が浅い状態で自社で行うのは非常に難しいです。SEOを外注することで、外注先は結果を出すためにさまざまな施策を行ってくれます。
外注するメリットをきちんと理解していないと、結果が出るのか不安で躊躇してしまうと思いますので、SEOを外注するメリットをご紹介します。
まず、結論からお伝えすると、SEOを外注するメリットは以下になります。
- 知識をもったプロが行うので、より高い成果を出せる可能性がある
- そのため結果的に費用対効果が高く、また結果が出るのが早い
外注先の担当者はSEOに精通したプロのため、サイトに合わせたSEOを的確に行うことで自社で行うよりも、売上やアクセスを伸ばせる可能性が高くなります。
また、Googleのアルゴリズムは定期的に更新されるため、その都度対応が必要になります。しかし、SEOに関する知識がなければ、どのような対応が必要か把握することも難しいです。
自社でSEOを行う選択をする場合は、費用削減が主な理由になるかと思いますが、自社で行うことが必ずしもコスト削減に繋がるとは限りません。自社で行う場合、社内スタッフが手を動かすことになるため、外注するよりも時間がかかり担当者の人件費かさむからです。
外注すれば外注費用はかかりますが、自社で行うよりも時間を削減できるだけでなく、結果も早く出て、費用対効果が高くなる可能性も十分にあり得ます。
SEOの外注をご検討の方は、SEOのプロである株式会社ヒトノテにご相談ください。これまでさまざまな業種・規模のWebサイトをコンサルティングしてきた経験を活かし、今本当に必要な施策を提案いたします。
株式会社ヒトノテでは、Webサイトの設計からコンテンツの制作まで、フルオーダーメイドのサポートが可能です。目的や予算に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
SEOの内部施策を外注する費用や相場感
SEOの内部施策を外注する場合の費用は、企業やサイトの規模感によってさまざまです。
実施する施策の内容にもよりますが、相場感は月額で数十万円から数百万円程度になると見ておいたほうがいいでしょう。1社だけ話を聞いて決めるのではなく、失敗しないためにも複数の外注先の候補を出して、見積もりを比較することをおすすめします。
また、単に費用が安ければいいわけではありません。費用が作業範囲に見合っているのか、担当者とのやり取りやコミュニケーションはスムーズかなど、さまざまな観点から確認すると失敗するリスクが減ります。
まとめ
SEO内部対策とは、サイト内のコンテンツやソースコードなどに着目した施策のことです。SEO内部対策を行うことにより、検索エンジンのクローラーがウェブサイトを正確に理解できるようになります。
クローラーが正確にウェブサイトを理解すれば、正しいインデックスを行うことができ、検索順位にも良い影響を与えるでしょう。
具体的な内部対策には、内部リンクの設置やtitleタグの最適化、モバイル最適化などの方法があります。それらに取り組む際には、重複コンテンツや隠しリンクなどに注意が必要です。
内部対策の方法がわからない方や効果的に運営したい方は、株式会社ヒトノテにご相談ください。
▼関連記事
表示速度はSEOにとって重要!計測方法&改善方法の事例をご紹介
効果的なSEO戦略とは?考えるべき4つのポイントとSEOテクニック
AMPのSEO効果と仕組み、マークアップ方法などをご紹介

執筆者:ヒトノート編集部
株式会社ヒトノテのオウンドメディア、WEBマーケティングの学習帳「ヒトノート -Hito note-」の編集部。

監修者:坪昌史
株式会社ヒトノテの代表取締役CEO。 エンジニアとしてキャリアスタートし、サイバーエージェントのSEO分析研究機関を経て、リクルートの横断マーケティング組織のマネージャー&全社SEO技術責任者を務める。その後、独立しSEOを中心としたクライアントの課題解決を行う。2017年、株式会社ヒトノテを創業し、様々な企業のウェブマーケティングの支援を行う。
おすすめの関連記事
─ 記事カテゴリから探す ─
元リクルートのSEO責任者へ無料相談
人気記事ランキング
-
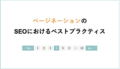
2024.04.25
ページネーションのSEOにおけるベストプラクティス
-
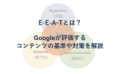
2024.04.22
E-E-A-Tとは?Googleが評価するコンテンツの基準や対策を解説
-

2021.12.06
レスポンシブデザインの最適ブレイクポイントとは?メディアクエリの書き方も解説
-

2021.12.22
【徹底比較】さくらのクラウドとAWSの特徴・機能・料金の違いを解説
-

2021.07.09
Webコンテンツにおける正しい引用の書き方をマスターしよう!
-
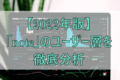
2022.02.21
「note」のユーザー数や年齢層を徹底分析!【2022年版】
-

2022.03.10
Googleインデックスの登録・確認方法を解説!サーチコンソールを使ってクロールリクエストしよう