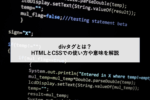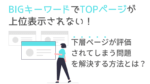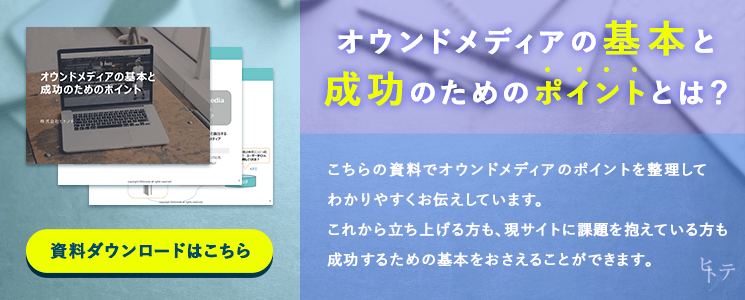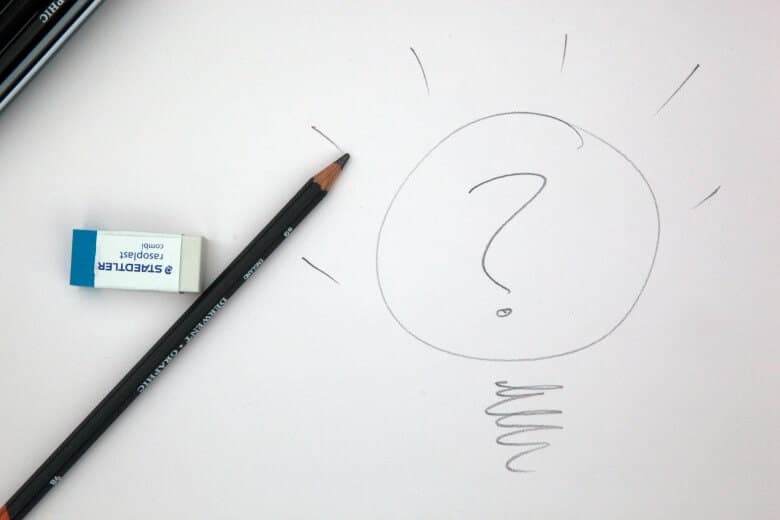Googleペナルティとは?対処方法や原因についても解説!
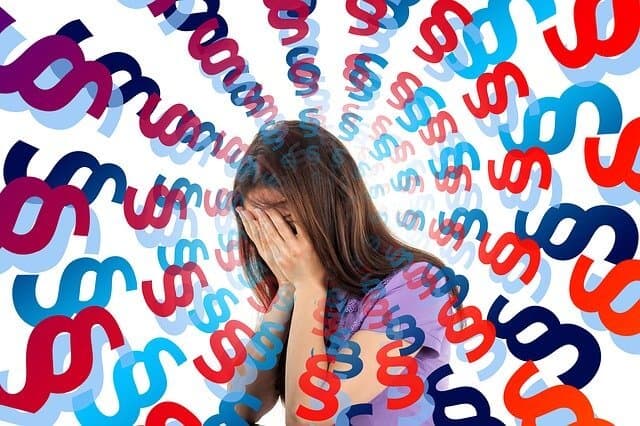
Googleペナルティとは、ウェブサイトが不適切な方法でSEOを実践すると課されるペナルティです。ペナルティを受けると、ページのランキングが急落する可能性があります。
この記事では、Googleペナルティの定義からその種類、発生の原因、そして適切な回避策をまとめています。GoogleペナルティからWEBサイトを保護するための具体的な手法についても掘り下げますので、ご自身のサイト運営にご活用ください。
検索エンジンの詳しい仕組みについてはこちらの記事をご覧ください
・検索エンジンの仕組みについてわかりやすく説明!
この記事の目次
Googleペナルティの種類
冒頭で、SEOの結果、Googleからペナルティを受ける可能性があることを紹介しました。Googleによるペナルティは、大別すると自動ペナルティと手動ペナルティの2種類に分けられます。
では、それぞれについて解説していきます。
自動ペナルティ
まずは、自動ペナルティについて解説します。
Googleは絶え間なくネット内を回遊しながら日々検索順位を変更しております。いわゆるクローラーという名のGooglebotというアルゴリズムによる順位付けを行なっているわけです。
そして、自動ペナルティとは、このクローラーのアルゴリズムにより自動で行なわれるペナルティのことを指します。
自動ペナルティを受けた場合は、対象ページの検索順位が下がってしまいます。検索結果に表示されなくなる(インデックス削除)ことはありません。
自動ペナルティを受ける要因としては、キーワード多用、コピーコンテンツ、内容不十分などが挙げられます。最大の注意点としては、自動ペナルティにより検索順位が下がっても一切通知が来ないことが挙げられます。
つまり、自動ペナルティを受けたかどうかは自分で確認するしかないということなのです。
手動ペナルティ
次に、手動ペナルティについて解説していきます。
手動ペナルティの場合は、Google担当者がサイトを目視した上で行っています。つまり自動ペナルティと手動ペナルティの最大の違いは、判定を下しているのが、botか人間かか、という部分です。
また手動ペナルティの場合、サーチコンソール経由で警告通知が来るのが特徴です。原因としては、不自然な被リンクや発リンク、低品質なコンテンツなどさまざまあります。
さらに手動ペナルティの場合は、順位の下落だけではなく検索結果にも表示されなくなるという重い処罰が下るのも特徴です。手動ペナルティには期限があり、再審査リクエストを一定期間放置すると解除されることがありますが、放置していると再度ペナルティを受ける恐れがあるので修正は必須です。
警告をよく読み、問題の箇所を修正後、必ず再審査リクエストしておきましょう。
Googleのペナルティの確認方法(ペナルティ診断)
ここまで自動ペナルティと手動ペナルティの大まかな違いを解説しました。
前述したように自動ペナルティの場合は通知が来ないので注意が必要です。
確認方法としては、主に「サーチコンソールで確認する方法」と「順位状況やインデックス状況を確認する方法」の2種類があります。
それぞれについて解説していきます。
方法➀ Googleサーチコンソールで確認する
ペナルティを課せられているかどうかの確認方法として、まずはじめに紹介する方法は、サーチコンソールで確認する方法になります。
ほとんどのサイト管理者や作成者はサーチコンソールを導入していることと思いますので、サーチコンソールを開いてみて、サーチコンソールの左メニューに「手動による対策」という項目を押すことでペナルティを受けているかどうかを確認することができます。
ただし、この場合ですと自動ペナルティまでは確認できませんので、あくまで通知メールを見逃していた場合などの手動ペナルティの確認のみとなっています。
それでは、次に自動ペナルティを課せられているかどうか確認する方法を紹介しましょう。
方法➁ 順位状況やインデックス状況を確認する
自動ペナルティの場合は、特にこれといった警告もなくGoogleのアルゴリズムの判断で検索順位を下げられている状態ですから、まずは自分のサイトを定期的に検索することで状況を把握することができます。
つまり、自動ペナルティを課せられているかどうかを確認するには、検索順位チェックツールや目視などで、検索順位やインデックス状況を定期的に確認することしかないのです。
ただしこの時、明らかに順位が大きく下落していたり、突然インデックス削除されていたりした場合などは、手動ペナルティを受けている可能性もあります。そのような時は、前述したサーチコンソールで手動ペナルティが課せられていないかの確認が必要になります。
自動ペナルティを課せられている場合の一番のネックとしては、たとえ明らかに検索順位が下がっていたとしても「どこに問題があるのか?」までは教えてくれないことです。パッと見では問題個所はわからない場合が多々ありますから、1つ1つ自身で発見し改善していく必要が出てきます。
Googleのペナルティ対象となるSEO施策
ここまで自動ペナルティと手動ペナルティについて、特徴とチェック方法などを解説してきました。
そこで次に、避けるべきSEO施策の知識として、ペナルティ対象となるSEO施策について解説していきます。
作為的な被リンクの作成(リンクプログラム)
作為的、意図的にリンクを作成する行為は、Google公式ガイドラインにおいて、スパム行為と見なされています。作為的にリンクを受ける行為をGoogleではリンクプログラムと呼んでおり、リンクプログラムに該当する行為は以下のURLにて定義されています。
例えば、以下のような行為が悪意あるリンクプログラムだと見なされます。
- ・被リンクの売買によってリンクを集める行為
- ・相互リンクページを作って被リンクを大量に集める行為
- ・ブログやブックマークサイトから大量にリンクを集める行為
- ・ウィジェットにリンクを埋め込んでリンクを集める行為
- ・テンプレートを配布してリンクを埋め込む行為
被リンク対策しませんか?というSEO業者さんが未だにいますが、上記の通り対価を払って被リンクを獲得する行為はGoogleのガイドライン違反になります。
リンクプログラムに該当すると見なされた場合、順位の下落または検索ページから排除される事もありますので、ガイドラインに反する手法は取らないように気をつけましょう。
良質な被リンクを増やす方法はこちらの記事に書いてあります。
・良質な被リンクを増やす方法は?初心者にもわかりやすくSEOに有効な方法を紹介
自動生成されたコンテンツ
プログラムを使ってサイトの文章を自動で生成し、ページを大量に作成する行為やRSSフィードなどを利用して自動生成する行為などが「コンテンツの自動生成」に該当します。「コンテンツの自動生成」に関するガイドラインは、Googleの「ウェブ検索のスパムに関するポリシー」から確認できます。
コンテンツ量が多いほうが良いというアルゴリズムを逆手に取って、生まれたブラックハットSEOの一つです。
現在は検索エンジンの精度が高まっており、不自然な文章や複製した文章などが検知されるようになっており、文章を自動生成しているとみなされたらペナルティを受けます。
隠しテキスト・隠しリンク
今ではほとんど見られませんが、ブラックハットSEOが横行していた時代に隠しテキストや隠しリンクという手法を行う人たちがいました。
例えば、背景色と文字色を同化させてテキストやリンクを隠してキーワードを乱発したり、ユーザーに表示させる画面外にテキストやリンクを大量に埋め込んだりします。
当時の検索エンジンは今ほど精度が高くはなく、キーワードを乱発するだけで順位が上がった時期もあったのです。
しかし、現在の検索エンジンは隠しテキストや隠しリンクを行っているかを判断できるようになり、今ではこういった手段を行ったサイトに対してペナルティを課すようになっています。
詳細はこちらの記事をご覧ください
・隠しリンクとは?代表的な手法や見つけ方からSEOでの影響まで解説!
・隠しテキストとは?やってはいけないペナルティ対象のSEOについて解説! ヒトノート -Hito note-
コピーコンテンツ
他サイトから文章をコピーしたり、サイトを複製するとコピーコンテンツと見なされ、ペナルティ対象となります。安易に他者のコンテンツをコピーし、コンテンツの量を増やそうと悪巧みする人がいたため、コピーしていないかチェックするアルゴリズムが組み込まれました。
そもそも他者のコンテンツをコピーするという行為は、アルゴリズムなど関係なく違法な行為ですので、くれぐれもコピーしないように注意しましょう。
・ミラーサイトとは?リスクやチェック方法、評価を下げないための作り方まで徹底解説!
参考にしたうえで、自らの言葉で文章を書く分には問題ないですが、参考にした結果似てしまってコピーと見なされないか、気になるとう人はコピーチェックツールなどで確認すると良いでしょう。
コピーチェックツールは、CCDのようなサイトがありますので参考にしてみてください。
キーワードの乱用
検索上位にしたいキーワードを不自然に繰り返し乱用する行為は、「キーワード乱用」と見なされペナルティ対象となります。無理にキーワードを詰め込もうとせず、読んでいて違和感のない自然な文章を作るようにしてください。
不自然なキーワード乱用例については、Googleガイドラインページの「無関係なワード」にて確認ができますので、気になる人は参考に読んでみてください。
キーワードを入れようと意識して無理やり詰め込まなければ、このような文章にならないので、普通に文章を書けば問題ありません。
クローキングされた画像
クローキングとは、クローラーとユーザーに異なるページを表示させる行為のことです。
クローラーはページのコードを見ていますが、人間はコードではなく表示されたページのほうを見ます。このとき、テキストと人間に対して違う表示がなされているとなれば、ペナルティの対象となるわけです。
クローキングは、2011年にガイドライン違反であるとGoogleは明確に言及しています。
現在でも大人向けのサイトなどで見かけることがありますが、例えばユーザーにだけ見える画像などもペナルティ対象となります。
クローキングについては、下記の記事で詳細に解説しています。より深く知りたい方は参照してください。
・クローキングとは?ペナルティになってしまうスパム行為について徹底解説
【参考】その他の原因
他にペナルティを課せられる行為として、不正なリダイレクトが挙げられます。
通常のリダイレクトは、サイトやページが移転した場合などですが、ペナルティを課せられるのは「全く違うサイトやページ」にリダイレクトさせた場合になります。
ペナルティを課せられる行為を総括すると、意識的か無自覚的かはともかく結果的に「Googleやユーザーを騙す行為」ということになるでしょう。
次に、ペナルティの解除方法を解説します。
ペナルティの解除方法
最後に、ペナルティの解除方法を解説していきます。
基本的には、検索順位低下やインデックス削除といったGoogleペナルティは解除することが可能です。
自動ペナルティと手動ペナルティでは対処法が違うため、それぞれ解説していきます。
自動ペナルティの解除方法
まず自動ペナルティの解除方法から解説していきます。
自動ペナルティの場合は、そもそも何が問題点かわからない場合が多々あります。その為、まずは前述したペナルティ項目にあてはまるようなペナルティ要素がないかどうか、ひとつひとつ確認していく作業が必要です。
何かしらのペナルティ要素を発見し問題点が判明したら、サイトやページを改善する作業に着手します。
改善後、再審査のリクエストが無い為、その後は待機することになります。ただしサーチコンソールで再度インデックス登録することは有効ですから、リクエストしておきましょう。
その後、定期的に検索順位チェックツールや目視で確認しながら、検索順位が上昇するのを待ちます。
手動ペナルティの場合
次に、手動ペナルティの解除方法について解説します。
手動ペナルティの場合は、前述したように放置すれば自動ペナルティよりも重いペナルティを課されます。
手動ペナルティの場合、基本的にはじめにサーチコンソールから問題点が指摘された警告通知が届きます。
警告には問題個所が指摘されて、箇条書きで記載されていますから、その内容をよく読んで、その通りに問題個所を修正し改善すれば問題ありません。
問題個所を修正し改善後、サーチコンソールで再審査のリクエストをします。手動ペナルティの場合は、解除までおよそ1週間かかるとされています。
まとめ
この記事では、SEOにおいてペナルティとなるガイドラインに反する行為について紹介しました。
他にもプログラムを組んで行うスパム行為などがガイドライン違反として禁止されていますが、これらは一般の人ができるような方法ではないので今回は割愛しました。
アルゴリズムの弱点を突いて無理に順位を上げようとせず、ユーザーが求める良いサイトを作ろうと意識していれば、ペナルティに抵触することはまずありません。
良いサイトやコンテンツを作ることが大事だと改めて認識して、取り組んでいきましょう。

執筆者:山本卓真
株式会社ヒトノテのSEOコンサルタント。事業会社でのWEBマーケティングの広い知見と経験をもとにクライアントと伴走することが得意です。

監修者:坪昌史
株式会社ヒトノテの代表取締役CEO。 エンジニアとしてキャリアスタートし、サイバーエージェントのSEO分析研究機関を経て、リクルートの横断マーケティング組織のマネージャー&全社SEO技術責任者を務める。その後、独立しSEOを中心としたクライアントの課題解決を行う。2017年、株式会社ヒトノテを創業し、様々な企業のウェブマーケティングの支援を行う。
おすすめの関連記事
─ 記事カテゴリから探す ─
元リクルートのSEO責任者へ無料相談
人気記事ランキング
-
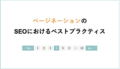
2024.04.25
ページネーションのSEOにおけるベストプラクティス
-
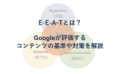
2024.04.22
E-E-A-Tとは?Googleが評価するコンテンツの基準や対策を解説
-

2021.12.06
レスポンシブデザインの最適ブレイクポイントとは?メディアクエリの書き方も解説
-

2021.12.22
【徹底比較】さくらのクラウドとAWSの特徴・機能・料金の違いを解説
-

2021.07.09
Webコンテンツにおける正しい引用の書き方をマスターしよう!
-
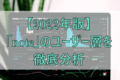
2022.02.21
「note」のユーザー数や年齢層を徹底分析!【2022年版】
-

2022.03.10
Googleインデックスの登録・確認方法を解説!サーチコンソールを使ってクロールリクエストしよう