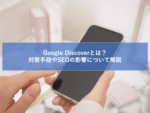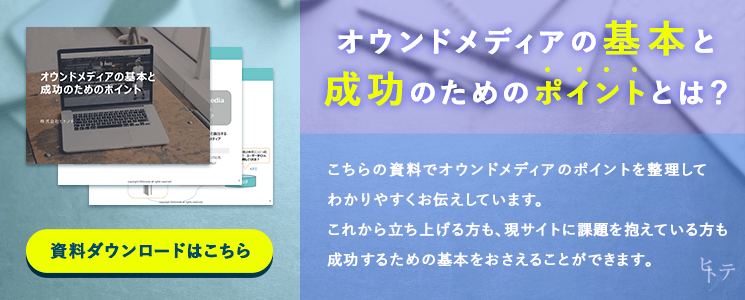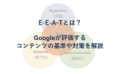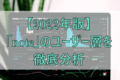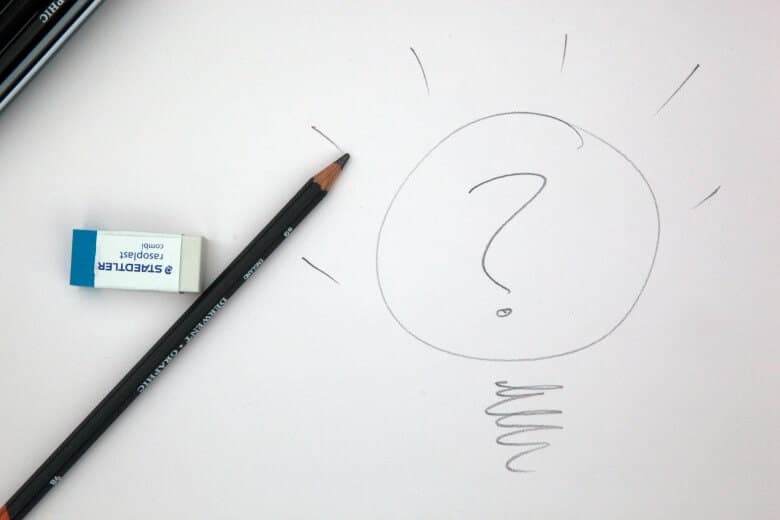ホームページリニューアルを成功させるには?方法・手順や判断基準を徹底解説

Web上の会社やサービスの玄関口にあたるホームページは、定期的にリニューアルして、最新の情報を載せたり、ユーザーが使いやすい仕様にしたりする必要があります。
ホームページを効果的にリニューアルすることで、アクセス数や問い合わせの増加につながります。
ホームページリニューアルを成功させるためには、正しい知識と対策方法が必要です。
本記事では、ホームページリニューアルの方法や手順を詳しく解説します。リニューアルするべきかどうかの判断基準や注意点も紹介するので、参考にしてください。
この記事の目次
ホームページリニューアルが必要な状況とは?
ホームページには、情報が煩雑になっている、デザインが劣っている、コンバージョンがないなど、リニューアルをしたほうが良い状態というものがあります。この記事では、ホームページをリニューアルすべき状態をご紹介するので、是非ご自身のホームページと照らし合わせながらご確認ください。
レスポンシブ対応になっていない
スマホユーザーが多くなっている2020年現在では、ホームページのレスポンシブ対応は必須です。レスポンシブ対応とは、ホームページを閲覧する端末の表示幅に応じて適切な見た目へと変化するデザインのことです。
ホームページをパソコンから閲覧した時と、スマホから閲覧した時の両方に適切なデザインで表示されるために、レスポンシブ対応は重要です。
レスポンシブ対応を行っていないと、閲覧する端末で表示が崩れてしまう可能性があります。表示が崩れてしまうとコンテンツが閲覧しづらく、ユーザーは早期に離脱してしまいます。
また、SEOにおいてもレスポンシブは重要です。Googleは「モバイルファーストインデックス」とよばれる検索順位計算方法を採用しています。これは、スマホサイトを基準にして順位決めを行うというものです。レスポンシブ対応しておらず、パソコンで閲覧することを前提としているデザインですと、検索順位に影響します。
情報が古く、大きく変更が必要
ホームページに掲載している情報が古いと大きく分けて以下のデメリットがあります。
- ユーザーに対してのデメリット:イメージダウンにつながる
- 検索に対してのデメリット:検索順位が下がる
ユーザーが訪れたホームページに古い情報しかなく、新しい情報が見つからない場合、ユーザーは更新されずに放置されていると判断し、不審を抱く方もいるでしょう。
例えば、企業ホームページの場合は、まだ経営を続けているのか疑問に思う可能性がありますし、ホームページは会社の顔でもあるため、古い情報しかないとイメージダウンにつながりかねません。
また、検索エンジンは新しい情報を評価する傾向にあるため、古い情報しかホームページに掲載していないと検索エンジンからの評価が下がり、検索順位にも影響を及ぼしてしまいます。
競合と比較した際にデザインが劣って見える
WEBデザインはファッションのトレンドのように移り変わりが激しく、ホームページを作成した当時は最新のデザインであっても、数年もすれば古いと感じられてしまうことも多いです。
競合サイトが最新のWEBデザインで制作されている中、自分のホームページが時代に遅れたWEBデザインで制作されていた場合、ユーザーに与える印象は弱くなりがちです。場合によっては、「この会社は本当に信頼できるのか?」と不安を持たれてしまうこともありますし、せっかくのユーザーを最新のWEBデザインで制作されている競合に奪われることも考えられるでしょう。
ユーザーから見たら、古いデザインのサイトよりも最新のデザインで制作されたサイトの方が活動に力を入れているように見えるので、信頼感と安心感を与えるはずです。そのため、定期的に最新のWEBデザインに合わせたリニューアルすることをおすすめします。
情報が整理できていない
ホームページを長期間運営し更新を続けていくと、それに伴いページ数も増えていきます。そして、情報量が増えていくごとに管理が難しくなる傾向にあります。情報整理ができていないホームページは、ユーザーが求めている情報を探しにくく、目的の情報に辿り着けないこともあります。
コンテンツが複雑化して情報が整理できていない状態は、カテゴリの変更やタグの整理、ナビゲーションの修正など小手先の改善では整理できない状況に陥っている可能性が高いです。
コンテンツが煩雑になり手に負えなくなっているのであれば、ホームページのリニューアルで、根底から構成を見直していく作業が必要でしょう。
ホームページ経由のコンバージョンがない
ホームページを運営する上でコンバージョンの設定は必須といえます。コンバージョンとは、ホームページを通して最終的にユーザーに行ってほしい行動のことです。コンバージョンが明確に設定されていないと、ホームページ上でユーザーにしてほしい事が不明確となり、当然ながらお問い合わせなどが増えることもありません。ホームページ運営の方針が決まっていないともいえるので、迷走する可能性もあります。
そのため、コンバージョンを設定していない場合は、まずホームページを通してどういう目的を達成したいのかを考えましょう。そして、その目的を達成するにはどのようなリニューアルをすればよいか逆算して、リニューアルを進めましょう。
更新が煩雑で運用がしにくくなっている
2020年現在、ホームページはCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)の導入が主流になっています。WordPressはご存知の方も多いと思いますが、これもCMSの一種になります。
もし、CMSを使わずにホームページを運用している場合は、直接HTMLの編集を行うことで情報の更新をしなければならないため、非常に手間がかかりますし、運用担当者が慣れていない場合は思った通りにコンテンツが表示されないなどのミスを生む原因になります。
更新作業が煩雑で運用しづらくなっている場合は、CMSを導入して構築し直すのが無難でしょう。
前回作成時から年数が経ちすぎている
現時点でコンバージョンやアクセス数の低下など、ホームページを運営している中で特に気になる点がなかったとしても、立ち上げから長期間経過している場合は、気づかないうちに上で列挙したような問題が起きている可能性があります。
また、ホームページのリニューアル周期の目安はBtoBでは5年、BtoCでは3年といわれています。そのため、リニューアル周期目安を超えて運用しているのであれば、リニューアルを検討した方が良いでしょう。
ホームページリニューアルのメリット
ホームページをリニューアルしたいと思っても、具体的にどんなメリットがあるのかわからないと実行しにくいと思います。リニューアルの代表的なメリットは「情報整理ができる、運営がしやすくなる、デザインを変更することで印象向上」などが挙げられますが、ここではそれぞれのポイントをご説明します。
情報を整理できる
ホームページは運営期間が長いほどコンテンツや情報量が増え、構造も複雑化します。コンテンツを追加して運営していくと最初は想定していなかったカテゴリの追加が必要になったりもします。そのため、どうしても初期のホームページ構成と異なってきてしまうのです。
しかし、リニューアルすることによって、不要と思われるコンテンツを削除するきっかけにもなるので、ホームページのコンテンツを取捨選択でき、構造の再配置など情報整理が可能になります。
また、上記でご説明した、最初は想定していなかったカテゴリの追加も、リニューアルに伴って新しく構造を設計することにより、他のコンテンツと整合性が取れます。
運営がしやすくなる
2020年現在では、ホームページ運用はWordPressを代表とするCMSによって行われることが多くなりました。
CMSを使用しないで静的なホームページを制作すると更新のたびにHTMLファイルをソースコードレベルで修正することになります。新しいコンテンツの追加や更新等を行う場合はマークアップスキルを持っている社内のホームページ運用担当者が行うか、保守契約を結んでいる制作業者に作業を依頼する必要があります。
一方、CMSはブログのように管理画面から更新が可能。コンテンツの追加や更新方法を覚える難易度も低いため、制作業者に更新を依頼しなくても自社内で完結出来ます。最低限のマークアップ方法を覚えていれば誰でもできるため、マークアップスキルのない人でも作業を行えるというポイントも見逃せません。
また、ホームページのリニューアルは更新するタイミングや手順など運用方法を見直すことにもつながりますので、運営しやすい環境を作れます。
最新のデザインでイメージ向上を図れる
最新のWEBデザインではなく古いデザインのままですと、イメージダウンにつながり、企業ブランドに悪影響が出る可能性もあります。
洗練された最新のWEBデザインに変更することによって、企業ブランドのイメージ向上にも役立ちます。
SEOを強化できる
検索エンジンの評価基準は定期的にアップデートされる仕組みになっており、それによって検索順位も変わります。先にも述べましたが、2020年現在では、Googleはモバイルサイトを基準に検索順位を決めています。そのため、レスポンシブに対応したホームページにすることによって、SEOの強化も可能です。
また、古いホームページですと旧来のマークアップ言語であるXHTMLで構築されていることがあるため、最新のHTML5で構築する機会になるのもリニューアルのメリットです。
XHTMLは2020年現在では古い言語であり、廃止されています。また、文法が厳格であるため、知識がない状態で触るときちんと表示できなくなるトラブルが発生することもあります。
また、HTML5は現在一般的に普及している言語であり、構成の意図を正確に検索エンジンに伝えることが可能なため、SEOとの親和性が高く、高い検索順位を狙えます。
レスポンシブ対応やHTMLを正しい構造で書き、検索エンジンに伝えるマークアップ方法に関しては、コンテンツの更新では対応できないため、リニューアルのタイミングでしか行えない重要な施策になります。
UI・UXを改善できる
ホームページリニューアルは、UIやUX改善を行うタイミングにもなります。使いやすいUIを用意しないと、せっかくホームページを訪れたユーザーの離脱率が高くなってしまうだけでなく、コンバージョン率も低くなってしまいます。
具体的な例を出すと、商品やサービスに対するお問い合わせや資料請求をコンバージョンとしている場合、分かりやすいボタンデザインや配置、快適な入力するフォームにしていないとコンバージョンにはなかなか結びつきません。
リニューアル前のホームページでUI・UXのどこが問題なのか洗い出し、改善することにより、ユーザーにとってストレスが少ないホームページになります。
UI・UXで重要なポイントはページ遷移のしやすさです。多くのホームページは、画面上部にメインコンテンツへの誘導をはかるメニューを用意しますが、画面上部だけではなく、フッター部分にもメニューを用意することで、コンテンツを読み終り、ページ下部まで到達したユーザーをほかのページに対して遷移を促すことが可能です。
アクセス数・コンバージョン数を改善できる
ホームページのコンテンツを適切に配置し、検索エンジンに適切な文書構造を伝えられるHTML5を使用することによって、SEOが強化されます。SEOが強化されると検索上位を狙えるようになり、アクセス数が改善します。
また、レスポンシブデザインを適用し、ユーザーが一番最初に見ることになるエリアであるファーストビューにより重要なコンテンツを配置するなど、UI・UXを考慮した作りにすることにより、ホームページを訪れたユーザーを逃さず、コンバージョン数を増やすことも可能です。
ホームページリニューアルの進め方
次に、自社のホームページをリニューアルするにあたって、事前に準備しておくことや、リニューアルを行っていく手順について解説します。
現状抱えている課題の棚卸しを行い、その課題を改善する方法を事前に明確にすることで、より多くのユーザーをホームページへ誘導し、かつコンバージョン数を増やすことができます。
ホームページリニューアル前にすべきこと
前述の「ホームページリニューアルが必要な状況とは?」で挙げた項目を振り返りながら、現在のホームページに足りないものや、改善や見直しが必要なことをまとめるところからスタートしましょう。
運用上のルールや新しい技術の導入、SEOにおけるGoogle検索アルゴリズムのアップデートなど、ホームページ制作に関する情報は日々更新されています。どういったトレンドがあるのか、ということも意識しておくと良いでしょう。
現状把握の過程では、他社のホームページも参考にしながらトレンドをつかむだけでは不十分です。自社のホームページがどういった課題を抱えているのか、ホームページを通してどのような目標を達成したいのか、現状のホームページのどの課題を解決することでその目標を達成できるのか、といったこともしっかりと把握することが重要です。
①課題認識
現在のホームページが抱えている課題は何なのかという現状課題の洗い出し作業は、その後のホームページリニューアルの方向性を定める非常に重要な作業です。
- レスポンシブ対応の有無
- 情報の鮮度
- UI・UXも見越したデザイン性
- コンテンツの運用手順
- コンバージョン状況
などの各項目について細かい調査を行う必要があります。
各項目の課題は、密接につながっています。社内だけでなく、ユーザー目線での確認も重要になります。Googleアナリティクスなどの分析ツールを用いて、ホームページ内でユーザーがどのように回遊しているのか、ユーザー導線も意識しながら課題抽出に取り組みましょう。
②目的設定
現状の課題を抽出したら、次は目的を設定しましょう。単に見やすくする、使い勝手を良くするといった抽象的な目的設定では、ホームページをリニューアルする上で「何を」「どのように」変えれば良いのか明確になりません。その結果、ホームページを通して何を伝えたいのかも曖昧になり、意図した成果が得られなくなってしまいます。
コンバージョンの内容を明確化し、誰もが目に見えるかたちで数値化できる目標を定めると共に、ユーザー視点での利便性や印象といった数値化しにくい内容についても検討しておきましょう。
③現状把握
現状の課題を洗い出し、リニューアル後の目的をリストアップすることで、目指すべきリニューアル後の姿と現状のギャップが浮かび上がってきます。課題を解決するには、それぞれの優先順位についても事前に決めておく必要があります。
ホームページリニューアルでは、予算的制約だけでなく、時間的成約も考慮しなくてはいけないため、上記の現状把握を踏まえて、より具体的なリニューアルプランを設計することが重要となります。
④プランニング
リニューアルにあたって必要となるプランニングとはどのようなものなのでしょうか。ホームページのリニューアルは決して一人で行えるものではありません。専門知識や豊富な経験を持つチームで取り組むことで、チーム内全体のナレッジを各段にアップさせることが期待できます。
リードタイムや予算に制約がなく、リニューアルを実施するケースはほとんどありません。限られた予算と時間の中で最大の成果を生み出すには、これまで述べてきた課題解決と目標設定を予算別、時間別に組み立てていくことが必要となります。
実際にホームページリニューアルを行う
ホームページのリニューアルを実施する上で、どういったことに注意し、どんな準備が必要か具体的にご説明します。
時間と費用をかけるリニューアルを成功させるためには、専門知識を持つ人材を中心として、柔軟に対応できる環境を整えておくことが必要です。また、リニューアル前後でのシステムの不具合や、社内外でのトラブルも事前に把握し回避できるようにしましょう。
⑤デザイン
WEBデザインを考える上で重要なのは、各ページを構成する色や文字サイズ、コンテンツの配置といった表面的なデザインだけではありません。ページ間の連動性や、ホームページ全体の構成といった、UI・UXを含めた視点も必要です。「使いやすさ」や「見やすさ」は、「買いやすさ」や「依頼のしやすさ」にも直結する要素です。そのため、デザイントレンドを取り込んだだけのホームページではなく、SEOやユーザビリティも考慮したデザインディレクションが不可欠となります。
⑥ページ制作
ページ制作においては、ドメイン(URL)、ページURLの変更に伴うリダイレクト処理、同じ内容のページが複数存在する場合のURL正規化といった、留意しておくべきポイントがいくつもあります。仮に、現状のホームページがA社に制作を依頼したもので、リニューアルの依頼先が別の制作会社であるB社だった場合、A社と交わしたソースコードの著作権に関する契約を確認しておかないと、トラブルが起きる可能性もあります。
ホームページリニューアル後に行うこと
ホームページのリニューアルが終わった後は、次に何をすれば良いか、何に注意が必要かをご説明します。
リニューアル前に行った現状把握と目的設定をもとに、その目的に沿って運用を開始すれば問題はありません。しかし、リニューアルから時間が経ってからでは意味のない、リニューアル直後にしかできないこともありますので、それぞれの内容について順を追ってご紹介します。
⑦告知
リニューアル後にまず実施したいのは、告知です。リニューアル直後から実施すると効果できであるため、リニューアル途中の段階で、リニューアル後の告知方法や内容、期間を決めておきましょう。
既存のユーザーだけではなく、リニューアル後に初めて訪問するユーザーへのアピールにもなり、事前に設定したコンバージョン達成のためにも重要なポイントとなります。
オンラインだけに留まらず、実店舗や関連施設などといったリアル店舗の連動企画として告知するのも良いでしょう。
⑧分析
リニューアル後に、各ページへのアクセス数やコンバージョン数を調べて、当初の予測と実績を比べることで、新たな改善点の把握と対策案を見つけることができます。
例えば、SEOによる効果を把握しながら検索上位表示を目指して継続的に改善を行ったり、レスポンシブデザインを導入し、UI・UXも考慮したリニューアルページが、どのような効果をもたらしたのか、ユーザーのサイト内の回遊状況を分析するなど、目的に合わせて様々な観点で分析をすると良いでしょう。
⑨改善
ホームページのリニューアル後、データ収集~分析を行う中で、リニューアル前には想定できなかった新たな改善点が見つかることもあります。
ユーザー属性の変化や、ユーザー属性ごとのページ滞在時間など、目標コンバージョン数値をクリアするために必要な補完情報の中に、より魅力的なホームページを運営していくためのヒントが隠されています。
改善点の中には、すぐに効果が出せそうなものから、改善までに時間を要するものもありますので、優先順位をつけて改善策を実施していきましょう。
制作会社に任せるとできること
ホームページのリニューアルを外部の制作会社に依頼すると、どんなメリットがあるのでしょうか。
リニューアルするためには、デザインやコーディングに関する専門知識やスキル、幅広い知見を持った人材が必要であるということをお伝えしました。
デザイナーやエンジニアが社内にいる場合、内製化してリニューアルを実施することも可能ですが、他の業界・業種の制作案件を多数手掛ける制作のプロに依頼することで、他社の事例やトレンドを踏まえながらリニューアルを進めることができ、内製化するよりも高い効果が期待できます。
制作会社が主に行うこと
次に、リニューアルを制作会社へ依頼する場合において、リニューアルの過程における具体的な作業内容を詳しくご説明します。
制作会社が担う業務範囲は会社によっても異なりますが、
- 現状把握と課題抽出
- ワイヤーにフレームの作成
- デザイン
- コーディング
- リニューアル後の運用
などが多いです。
リニューアルの目的やコンセプト、課題設定に基づき更新~精査を行った後は、各ページの構成(カテゴリやグローバルナビゲーションなど)を落とし込んだワイヤーフレームを作成します。
そして、作成したワイヤーフレームをもとにデザインを作成します。デザインを作成する際にも、そもそものリニューアルの目的をしっかりと把握し、SEOやUI・UX、企業ブランドのイメージ向上に繋がるようにします。
デザインが固まった後はエンジニアによりコーディングを行いリニューアルが完了します。リニューアル後も、会社によってはコンテンツの更新、SEO施策やコンバージョン率の改善施策の実施業務を行います。
上記が主たる内容であるとイメージしておくと良いでしょう。
リニューアルに伴い念頭に置いておきたいのは、制作会社へ依頼を行う場合でも、前述の現状把握~課題認識~プランニングは、自社でしっかり把握し、とりまとめておく必要があるということです。
その理由としては、ホームページのリニューアルは、経営の方向性を左右する重要な内容であり、それらを全て外部の制作会社に任せるわけにはいかないからです。
もちろん、社内でまとめた現状認識~課題設定~プランニング方法について、制作会社からのアドバイスを受けることは可能です。むしろ、依頼後の打ち合わせの中で、それらの内容を更にブラッシュアップさせながらリニューアルを進めることをおすすめします。
社内にデザイナーやエンジニアがいる場合でも、社外の制作会社のチームとやりとりを重ねながら、個々のスキルアップや知識向上に繋がるメリットもあります。
ホームページのリニューアルでよくある質問
リニューアルに対して疑問に感じるも多くあると思います。特に、ドメインやデータの引き継ぎ、URL変更に関しては、多くの方が疑問に思うことの一つかと思います。ここでは、ホームページのリニューアルでよくある疑問のポイントをご紹介します。
ドメイン(URL)は引き継げる?
一般的にドメイン(URL)は個人所有物になるため、ホームページをリニューアルしても引き継いで利用可能です。
ただし、リニューアル前とリニューアル後で契約しているレンタルサーバーを変更する場合、以下の条件に該当する場合は引き継ぎができません。
- ドメインを取得してから60日未満である
- ドメインの有効期限が切れている
基本的に今までホームページを運用してきて適切にドメインの有効期限を更新している場合、ドメインが引き継げないという状態にはならないと考えて良いでしょう。
現在のホームページのデータ(写真など)は引き継げる?
ホームページに掲載してある写真や文章などのデータの権利が運営者側に属している場合は、引き継ぐことが可能です。
一方、運営者ではない制作会社が作った画像や第三者に執筆してもらったものなど、著作権が他者に属している場合は、著作権者に再度確認する必要があります。譲渡されているのであれば運営者側のものになるため、自由に引き継ぐことができます。
各ページのURLは変えない方が良い?
基本的には、各ページのURLは変えない方が良いです。URLを変更する場合は、リダイレクト処理を入れて、URL変更前のページにアクセスされたときにURL変更後のページに飛ばす必要があります。そうしなければ、ユーザーはリニューアル前のページを見ることになってしてしまいます。
もし、リニューアル前のページが削除されていた場合は404ページが表示されます。ページにアクセスしたのにコンテンツが表示されなければ、企業のイメージダウンとなり、アクセス低下にもつながります。
また、リダイレクト処理の実装は、リニューアル時の作業量が増えるだけではなく、適切に動作しているか確認する工数もかかるため、完成まで時間がかかります。
これらのデメリットから、各ページのURLは変えないほうが無難です。
ホームページのリニューアルにおける注意点
リニューアルする際に注意しなければならないことは、制作業者変更の権利確認、ドメイン変更のリスク、リダイレクト処理、URL正規化など、たくさんあります。注意点について細かくご説明するので、後にトラブルとならないよう、ポイントをつかんでおきましょう。
制作業者変更に伴う権利の確認
前回制作を依頼した制作業者とは異なる制作業者に依頼する場合、注意しなければならないのが権利情報の確認です。例えば、ソースコードの著作権が自社ではなく制作業者にある場合、自社あるいは別の制作業者が改変してしまうと著作権侵害に該当してしまいます。
権利を確認せずに制作業者を変更してリニューアルを進めてしまうと著作権関連のトラブルが発生しかねませんので、しっかり確認しておきましょう。
ドメイン(URL)変更のリスク
ドメイン変更はおすすめしません。
ドメインを変更してリダイレクト処理をきちんとしないと、ドメインパワーがなくなってしまいます。ドメインパワーとはGoogleから得ているホームページの評価のことで、継続的にコンテンツを追加更新していくことによって蓄積され、ホームページに掲載しているコンテンツ全体の検索順位を上昇させる効果があります。
そのため、ドメインを変更すると育ててきたドメインの恩恵を受けられなくなるのです。
また、ドメインを変更する場合はメールアドレスの変更も必要になります。
メールアドレスが変更になると、名刺など印刷物は全て印刷し直す必要が出てきます。また、メールアドレスが変更されたことを取引先や現在連絡をとっている顧客に対して連絡しなくてはいけないため、非常に工数がかかってしまいます。
リダイレクト処理
上でも既に少し触れましたが、ホームページのリニューアルで忘れてはいけないのが適切なリダイレクト処理を行うことです。
リダイレクト処理が必要になる場面は大きくわけると以下になります。
- ページのURLを変更したとき
- ドメインを変更したとき
ページのURLを変更したら、古いURLでアクセスされたときに新しいURLに自動でリダイレクトするように設定しましょう。
例えば、旧ホームページでURL「work」に存在したコンテンツを「case」に移し、「work」を削除したとします。検索エンジンには、しばらく「work」へのリンクが表示されるため、アクセスすると404エラーが表示されてしまいます。
リダイレクト処理を行わないと検索順位も下がってしまいます。ユーザーからしても404エラーが出て見られないページがあると「このホームページは大丈夫なのか」とイメージダウンにも繋がります。
また、ドメインを変更した場合はリニューアル前のホームページにアクセスされたらリニューアル後のホームページに転送する301リダイレクトと呼ばれる処理を行わなければなりません。なぜなら、301リダイレクトを行わないとリニューアル前のドメインが保有しているドメインパワーを引き継ぐことができないからです。
ドメインは取得してから経過した時間に応じて、SEOの評価が上がります。そのため、古いドメインのドメインパワーを引き継ぐためにもリダイレクト処理が必要なのです。
URL正規化
ドメインを変更した場合は、URL正規化を行う必要があります。
URL正規化とは、同一コンテンツなのにも関わらず、複数のURLに分散してしまっているとき、URLを統一して検索エンジンにおける評価を集中させるSEO施策の一つです。
URL正規化を行わないと検索エンジンから受ける評価も分散してしまうため順位が下がり、コピーコンテンツとして分散されたいずれかのページがペナルティを受けてしまう可能性もあります。
まとめ
ホームページのリニューアルは、現在の状態を把握し抱えている問題を明確化してから、目的を設定します。このように目的から逆算して作業を行う必要があることが理解いただけたかと思います。
弊社は目的設定から逆算したホームページリニューアルに強みを持っています。無料相談を行っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

執筆者:ヒトノート編集部
株式会社ヒトノテのオウンドメディア、WEBマーケティングの学習帳「ヒトノート -Hito note-」の編集部。

監修者:坪昌史
株式会社ヒトノテの代表取締役CEO。 エンジニアとしてキャリアスタートし、サイバーエージェントのSEO分析研究機関を経て、リクルートの横断マーケティング組織のマネージャー&全社SEO技術責任者を務める。その後、独立しSEOを中心としたクライアントの課題解決を行う。2017年、株式会社ヒトノテを創業し、様々な企業のウェブマーケティングの支援を行う。