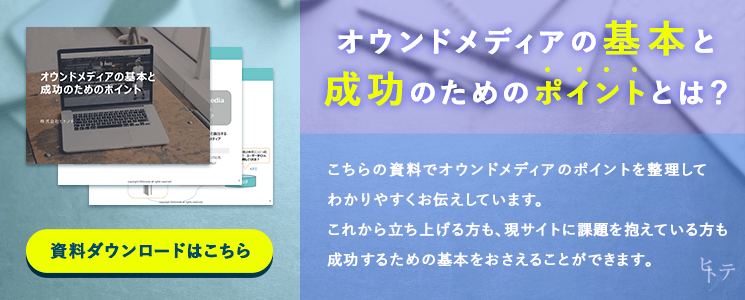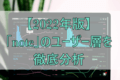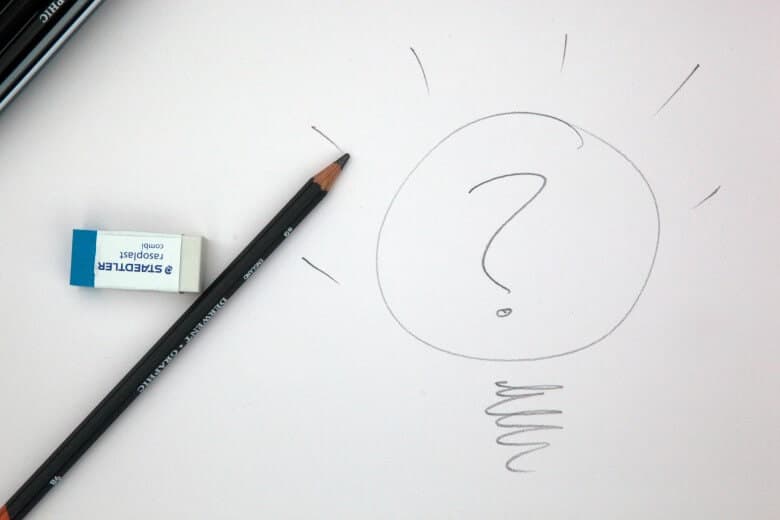URLの末尾につけるトレイリングスラッシュは必要?SEOへの影響や注意点を解説
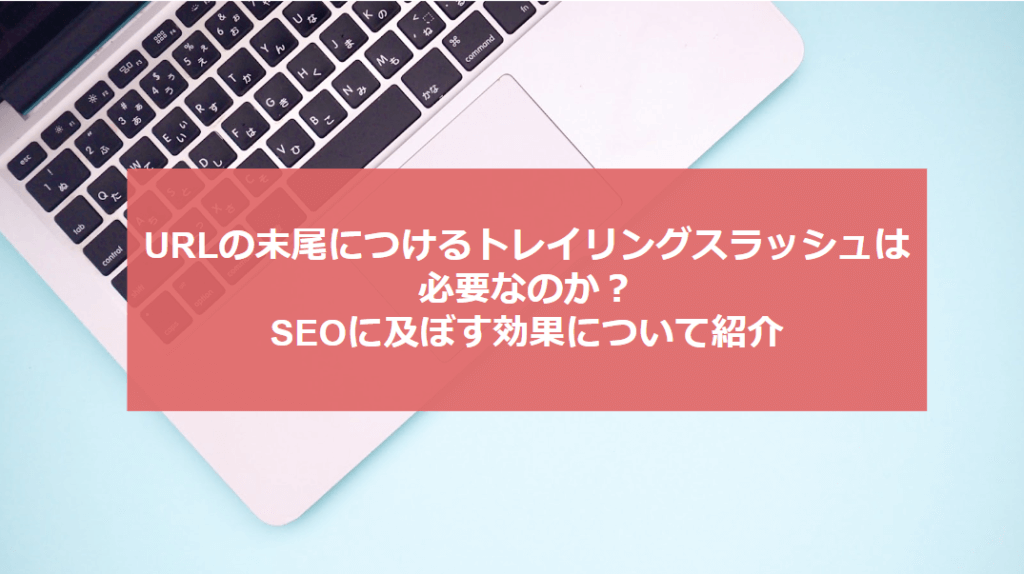
トレイリングスラッシュとは、URLの末尾につく「/」のことです。有無に関わらず同じページが表示されるケースが多いため、ユーザーは気にする必要はありません。一方でサイト運営側の立場だと、SEOへの影響が気になるでしょう。
結論、トレイリングスラッシュはSEOには影響しないといわれています。しかし、トレイリングスラッシュの有無が混在しているサイトでは301リダイレクトやcanonicalタグを用いてURLを正規化することが大切です。
また、ECサイトやポータルサイトのように階層構造が必要なサイトなど、トレイリングスラッシュをつけるべき場合もあります。
本記事では、トレイリングスラッシュの有無による違いやSEOに及ぼす効果、注意点をわかりやすく解説します。参考にしてみてください。
この記事の目次
トレイリングスラッシュとは?
トレイリングスラッシュとは、URLの末尾につくスラッシュ「/」のことです。
・トレイリングスラッシュあり:https://hitonote.jp/
・トレイリングスラッシュなし:https://hitonote.jp
URLは、アクセスするディレクトリやファイルを指す情報であり、「インターネットの住所」とも呼ばれています。そしてURLの中の「/」は、住所における「○丁目」や「番地」のようにフォルダの階層を示しており、トップページ以外の下層ページにアクセスする際に必要です。
例:https://ドメイン/ディレクトリ/ファイル
一方でトレイリングスラッシュは、通常の「/」とは異なる意味を持っています。
トレイリングスラッシュの有無による違い
トレイリングスラッシュの有無は、ユーザーにとってほとんど関係ありません。しかし厳密にいえば、トレイリングスラッシュの有無によってURLにアクセスする際の処理方法などが異なります。
そのため、サイト運営者はトレイリングスラッシュの有無による違いについて理解しておくことが大切です。
ここからはドメイン名の後、あるいはサブディレクトリ後のトレイリングスラッシュの有無による違いを比較しながら解説します。
ドメイン名の後の場合
ドメイン名の後にトレイリングスラッシュがない場合、サーバー側はルートディレクトリ(階層のトップにあるディレクトリ)に格納されているドキュメントを返してくれます。
つまり、「https://hitonote.jp」で検索しても「https://hitonote.jp/」にリダイレクトされるため、トレイリングスラッシュの有無は処理上関係ありません。どちらもアクセス方法や表示されるページが同じであるため、ユーザーは気にする必要はないでしょう。
一方で、あり・なし両方のURLでアクセスできてしまう状態は、ミラーページと見なされる可能性があります。そのためサイト運営者は、301リダイレクトやcanonicalタグを用いてURLを正規化しておきましょう。
サブディレクトリの後の場合
サブディレクトリ後のトレイリングスラッシュについては、GoogleのJohn Muelle氏がTwitterで、(A)から(G)のURL一覧を例に挙げて見解を述べています。
そこでは、トレイリングスラッシュなしのURL(F)とありのURL(G)は「異なる(F is not G)」と結論付けられているため、やはりサイト運営者は両者の違いを理解しておくことが大切です。
・トレイリングスラッシュなし:https://hitonote.jp/column
・トレイリングスラッシュあり:https://hitonote.jp/column/
トレイリングスラッシュなしの場合、「column」という名前のドキュメント(ファイル)をリクエストするURLになります。つまり、「column」と名付けられた画像やHTMLなどにアクセス可能です。
一方でトレイリングスラッシュありの場合、「column」という名前のディレクトリをリクエストします。つまり、「column」ディレクトリの中にあるドキュメント(index.htmlなど)にアクセス可能です。
トレイリングスラッシュなしのURLが示すドキュメントが見つからなかった場合、検索エンジンがありの状態でリダイレクトする仕組みとなっています。リダイレクトは表示速度低下などにつながるため、ディレクトリをリクエストしたい場合はトレイリングスラッシュをつけておきましょう。
トレイリングスラッシュによって階層構造を示すことができる
ドメイン名のみの場合は常にトレイリングスラッシュありの状態でリクエストされるため、有無による違いはありません。一方で、サブディレクトリの後のトレイリングスラッシュには、ディレクトリとファイルどちらを示すのかという違いがあります。
また、データベースやポータルサイトなどでは、トレイリングスラッシュを用いることで階層構造を構築可能です。ここからは、トレイリングスラッシュをつけた方が良いケースとして都道府県ページを例に挙げて解説します。
A
①東京のページ
/tokyo/
②渋谷のページ
/tokyo/shibuya/
B
③東京のページ
/tokyo
④渋谷のページ
/tokyo/shibuya
Aは①②ともにトレイリングスラッシュがあり、Bは③④ともにありません。
この場合、AはURLの構造上「tokyo」の下に「shibuya」がいることになり、親子関係を示せています。一方でBは、「tokyo」と「shibuya」の親子関係が構築されていません。
③と④の親子関係を明示できないとSEOへの軽微な影響を及ぼす可能性があります。そのため、親子関係を構築したい(下層にページが存在する)ページに対しては、トレイリングスラッシュをつけることを推奨します。
また、④にアクセスする際に「shibuya」というファイルが見つからなかった場合、最終的に②のディレクトリを参照することになります。直接②にアクセスするよりも手順が1つ増えるため、SEOに影響を及ぼす可能性があります。Bの形にする明確な意図がない場合はトレイリングスラッシュをつけておきましょう。
トレイリングスラッシュの有無がSEOに及ぼす効果
結論、トレイリングスラッシュの有無がSEOに及ぼす影響は軽微とされています。トレイリングスラッシュあり・なしの異なるURLで同じページが表示されるため、重複コンテンツと見なされるのではないかと不安を感じる方もいるでしょう。しかし、サーバー側で自動処理されるためSEOへの影響はないといわれています。
とはいえ、トレイリングスラッシュでページの住所を明確にしておくことで損をすることはありません。最善のサイト運営をしたい方は、トレイリングスラッシュを使い分けてURLが混在しないようにしておきましょう。
トレイリングスラッシュは正しい表記で統一して階層構造がある場合は付ける
Googleの見解では、トレイリングスラッシュの有無はどちらでも問題ないとされています。しかしスムーズなサイト運営のためには、正しい表記で統一しておくのが無難です。
基本的にはトレイリングスラッシュありに統一し、必要に応じて301リダイレクトなどを活用しましょう。内部リンクなどでつなぐ際にも統一したルールに沿った設定を行う必要があります。
また、階層構造をGoogleに示したい場合は、トレイリングスラッシュをつけるようにしましょう。
トレイリングスラッシュの有無を統一する際の注意点
トレイリングスラッシュの有無はユーザーにとっては影響がないものの、サイト運営者は管理のために統一しておく必要があります。しかし、URLを正規化する際には気をつけるべきポイントがあります。
ここから紹介する2つの注意点を確認して、運営サイトのURLを更新していきましょう。
リダイレクト設定がされているか確認
前述のようにトレイリングスラッシュなしのページが見つからなかった際には、サーバー側でありの状態で処理されます。そのため、トレイリングスラッシュの有無はSEOに大きな影響を及ぼしません。
しかし、契約中のWebサーバーが「リダイレクトなし」に設定されている場合、「/」のない異なるページだと認識されて正しくアクセスできなくなってしまいます。そのためまずは、Webサーバーのリダイレクト設定を確認しておきましょう。
また、リダイレクト設定のないサーバーの場合には、「301リダイレクト」「canonicalタグ」を用いてURLを正規化する必要があります。
301リダイレクトとは、ユーザーがアクセスしたURLとは異なるURLに転送することです。トレイリングスラッシュのないURLにアクセスしたユーザーを正しいURLに転送できるため、PV増加などにつながります。
またcanonicalタグとは、重複したコンテンツを1つのURLにまとめる方法です。ユーザーの利便性を高めるだけでなく、検索エンジンからの評価を1つのページに集中させる効果も期待できます。
サブディレクトリの後ろにつけない場合は拡張子まで入れる
トレイリングスラッシュなしの場合でもサーバー側で自動処理されるため、トレイリングスラッシュありのページにアクセス可能です。しかし、指定したいドキュメントがある場合でも自動でリダイレクトされてしまうというデメリットもあります。
そのため、サブディレクトリの後のトレイリングスラッシュを意図的につけない場合は、URLの最後に拡張子をつけておきましょう。「.html」や「.pdf」などの拡張子をつけておくことで、リクエスト通りのページを表示することができます。
同一のドメイン内でトレイリングスラッシュの有無が混在していると、SEOなどの手間が増えることがあります。そのため、基本的にはトレイリングスラッシュありに統一し、意図がある場合のみトレイリングスラッシュなし(拡張子など)を用いるのが良いでしょう。
まとめ
結論、トレイリングスラッシュの有無はSEOに大きな影響を及ぼしません。ドメイン名のみの場合は自動的にトレイリングスラッシュありの状態で処理されるため、有無に関わらず同一ページにアクセス可能です。
しかし、サブディレクトリの後のトレイリングスラッシュは、有無によって指定するファイルやディレクトリが異なります。トレイリングスラッシュなしのページがない場合は、混在しないようにURLを正規化しておきましょう。
また、階層構造をGoogleに明示したい場合にはトレイリングスラッシュを付けることを推奨しております。運営しているメディアに適した形で運用するようにしましょう。

執筆者:ヒトノート編集部
株式会社ヒトノテのオウンドメディア、WEBマーケティングの学習帳「ヒトノート -Hito note-」の編集部。

監修者:坪昌史
株式会社ヒトノテの代表取締役CEO。 エンジニアとしてキャリアスタートし、サイバーエージェントのSEO分析研究機関を経て、リクルートの横断マーケティング組織のマネージャー&全社SEO技術責任者を務める。その後、独立しSEOを中心としたクライアントの課題解決を行う。2017年、株式会社ヒトノテを創業し、様々な企業のウェブマーケティングの支援を行う。