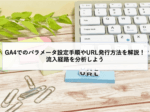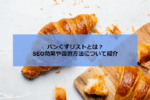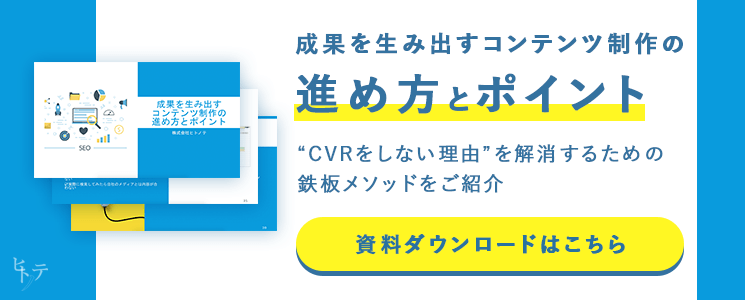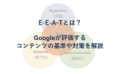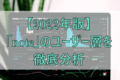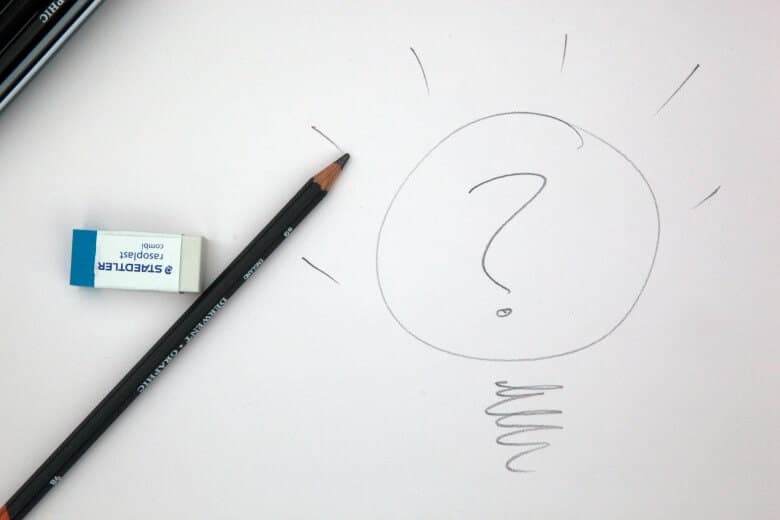コンセプトとは?テーマとの違いやビジネスにおける重要性を解説

コンセプトとは、一般的にベースとする考え方といった意味を持ち、ビジネスにおいては、製品やプロジェクトの内容や目的を抽象化した言葉として用いられています。製品やサービスの方向性や特徴を示すために使用され、ビジネス戦略やマーケティング戦略の基盤となるため、ビジネスにおいてコンセプトを明確にすることは非常に重要です。
一方で、コンセプトの意味やビジネスにおける重要性を正しく理解できている方は少ないのではないでしょうか?
本記事では、コンセプトの意味や重要性から具体的な作成方法やテーマとの違いまで詳細に解説します。
この記事の目次
コンセプトとは?テーマとの違い
コンセプトとは何か、そしてテーマとの違いについて説明していきます。それぞれの意味を理解し、本質的な違いをわかるようにしましょう。
コンセプトとはなにか
コンセプトとは、英語のconceptからきており、conceptをカタカナ読みにした言葉です。概念という意味を持ち、日本語でコンセプトを使うときは、ベースとする考え方のような意味で用いられます。また、一貫している考えという意味も持ちます。
コンセプトという言葉が使われるシーンについてですが、誰かに物事の内容や方向性を伝える際に用いられます。ありのままを話すのではなく、物事の内容や目的を抽象化した言葉がコンセプトです。
テーマとの違い
テーマはコンセプトと似た言葉として認識されていますが、意味が異なります。コンセプトは概念という意味を持つ一方、テーマは主題という意味を持ちます。コンセプトは主にマーケティングやクリエイティブな仕事に用いられることが多い一方、テーマは主題という意味を持つことから、議論の場で用いられることが多い言葉です。
あらゆる物事の大前提を一言で表しているのがテーマであるといえます。
ビジネスにおけるコンセプトの重要性
次に、ビジネスにおけるコンセプトの重要性について説明していきます。コンセプトを作成することによる代表的なメリットとして5つのことが挙げられます。なぜこのメリットが生まれるのかということを意識しながらコンセプトの重要性を理解しましょう。
ソリューションの創出を促す
ビジネスでは顧客に対して課題解決のための提案をしたり、施策を考えたりする場面が多くあります。そして、顧客の課題を解決するためには課題を知ることと、どんなコンセプト(概念、一貫した考え)で解決策を実行していくかが重要になります。
コンセプトがあることでスムーズに課題を解決することができ、顧客にも自社にも課題や解決策がわかりやすくなるメリットがあります。
ビジネスの骨組みになる
コンセプトを設計することで、ビジネスの骨組みを作ることができます。単純に「~が好きだから~のお店をやる」では上手くいかないことが多く、コンセプトをきちんと練ることが重要です。5W1Hで考え、独自性や自社ならではの強みをどう活かすかをコンセプトに組み込んでいきましょう。また、コンセプトを作成していくと、作成段階で将来性についての判断もできます。
5W1Hでコンセプトを作成すると…
5W1Hの考えでコンセプトを作成すると自社の強みをどう組み込むことができるのでしょうか。
例えば、これまで菓子の製造・卸売り業を行っていた企業がカフェ事業に挑戦するとします。その際に5W1hで強みや特徴を整理すると以下のようになります。
|
これらの強みや特徴を整理することで、事業の骨組みを組み立てながらコンセプトを作成することができるでしょう。
方向性が定まる
コンセプトを作成することで事業の方向性を定めることができます。方向性が定まることで、ブレが発生しづらくなり、また、設計の際のスピードも速まります。
例えば、新しく開店する居酒屋のコンセプトを「江戸時代の気分が味わえる」とした場合。内装は江戸時代をモチーフにしたものにしたり、提供するお酒を日本酒や焼酎などの日本人が昔から馴染みのあるものにしたりするのではないでしょうか。このようにコンセプトを決めることで、内装や提供するお酒の種類も決定しやすくなり、アイデアを形にするスピードも速まります。
新しい製品のヒントになる
コンセプトを作成することで、ターゲットのニーズをつかみやすくなります。また、新しい製品やサービスの細かい仕様を決めたり、大まかな方向性を決めたりする以外にも、ゼロから製品を生み出すヒントも得られるでしょう。
魅力的なキャッチコピーが生まれる
コンセプトは大々的に発表するようなものではなく、社内やプロジェクト内の人が理解し、ビジネスの進行を助ける役割を担っていればいいものと考えましょう。意図してキャッチコピーを作る必要はありません。コンセプトがきちんとしていると、自然と強みが見えてきて、その結果として強力なキャッチコピーが生まれます。
例えば、ダイソンは「吸引力の変わらない、ただ一つの掃除機」をコンセプトにしています。ダイソンは掃除機の「吸引力の低下」という問題点に着目し、吸引力が低下しないことをコンセプトにした結果、魅力的なキャッチコピーが生まれました。
コンセプトの作成手順
ここからはコンセプトの作成手順について説明してきます。それぞれのステップの意味を理解しましょう。
ターゲットを設定する
まず誰のための製品、サービスとするかを設定します。市場を分析し、どのような人がその製品、サービスを望んでいるかを分析することが重要です。自社のやりたいことを優先するのではなく、分析データをもとにコンセプトの作成を始めましょう。
課題を知る
ターゲットを設定したら課題を分析し、そこにどのようなアプローチを仕掛けるのかをコンセプトに盛り込んでいきます。複数の課題が浮かび上がったら、何が最も大きな課題かを分析していきましょう。
差別化をする
次に他社と自社の差別化を行いましょう。自社の強みをさらに強化するコンセプトにするのか、自社にないものを補おうとするコンセプトにするのかを考えます。事業内容によって、適時変えていくのも良いでしょう。差別化して浮かび上がったものに対して、最終的な製品・サービス設計をどうするか決定します。
コンセプトを作成する際のポイント
最後に、コンセプトを作成する際のポイントについて説明していきます。ただ手順に沿って作成するのではなく、ポイントを押さえて作成することでより有効的なコンセプトを作成することができます。
伝えたいメッセージを込める
伝えたいメッセージをコンセプトに込めましょう。伝えたいメッセージを込めることで、消費者はもちろん開発メンバーに対してのキャッチコピーとなり、一貫性や統一感が生まれます。コンセプトは消費者のみに向けたものではなく、製品やサービスに作り手の気持ちが込められます。もしメッセージがなければ、大まかな方向性は決まっても、細かいところで方向性のズレが生じるかもしれません。可能な限り、伝えたいメッセージは込めた方が良いでしょう。
どんな「価値」を提供したいか意識する
ビジネスではモノを通じて価値を提供することが本質になります。そのためコンセプトを作る際には、どんな価値を届けたいかを意識することが必要です。課題解決をするモノを作るためのコンセプトであるからこそ、価値をどうやって届けるか、だれに届けるかを意識して作成することが大事です。モノを通じて価値を提供することを忘れないようにしましょう。
自社のウィークポイントを知る
コンセプトを作成する際は、強みのほかに自社のウィークポイントを知る必要があります。
ウィークポイントを改善することで、より良い価値を提供できるかもしれないからです。そのため、どうしたらウィークポイントが改善され、コンセプトに則ったアプローチを実現することができるのかを考えましょう。また、ウィークポイントを改善することで、自社の独自性を象徴する強みに変わることもあります。
まとめ
今回の記事ではコンセプトの意味やビジネスにおける重要性、テーマとの違いについて説明しました。
コンセプトは概念という意味を持ち、日本語ではベースとする考え方のような意味で用いられます。コンセプトはビジネスにおいてソリューションの創出を促したり、ビジネスの骨組みになったりする重要なキーワードです。コンセプトを作成することで、新しい製品のヒントも生まれることがありますので、コンセプトを活用してこれまで以上の製品やサービスの開発を目指しましょう。